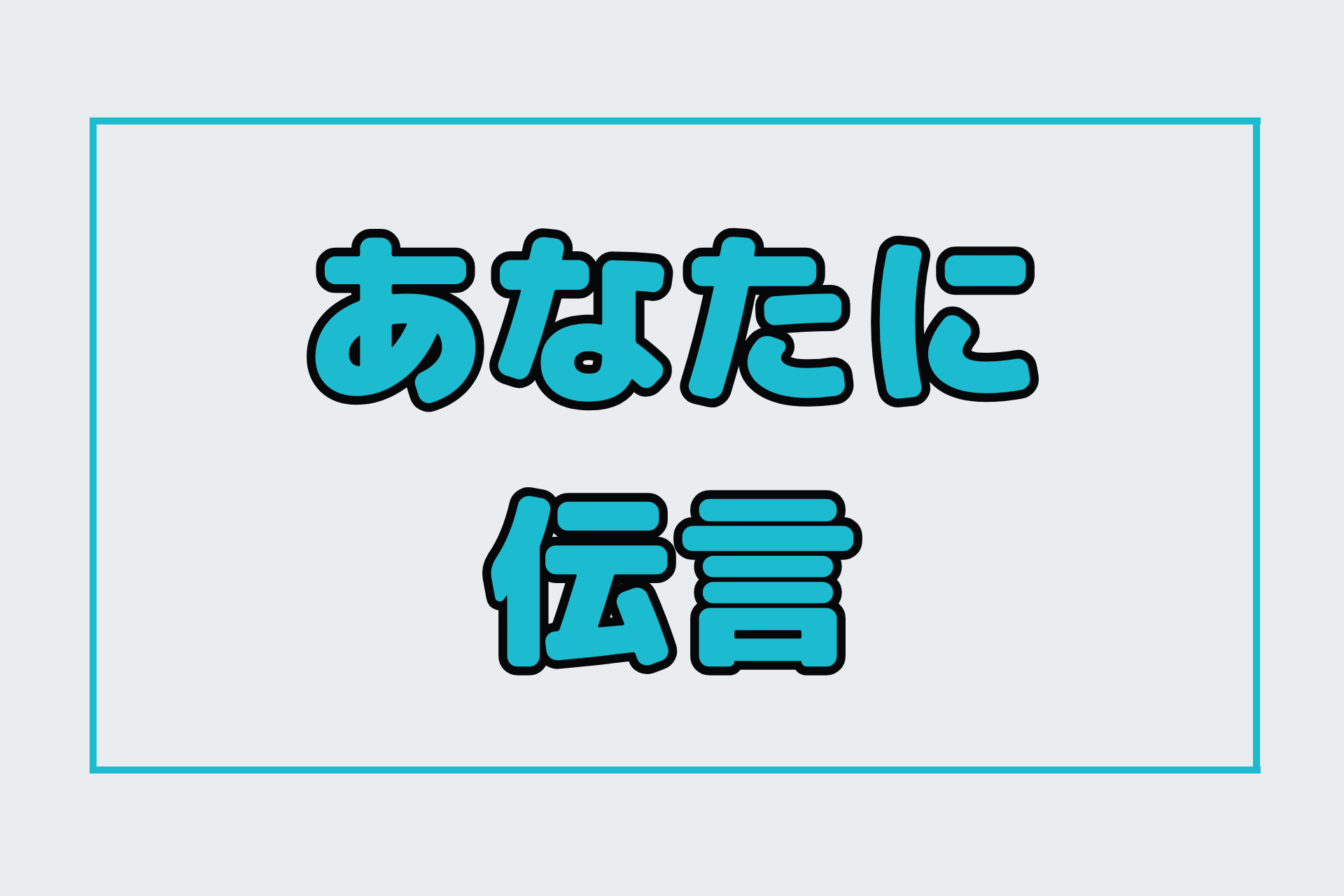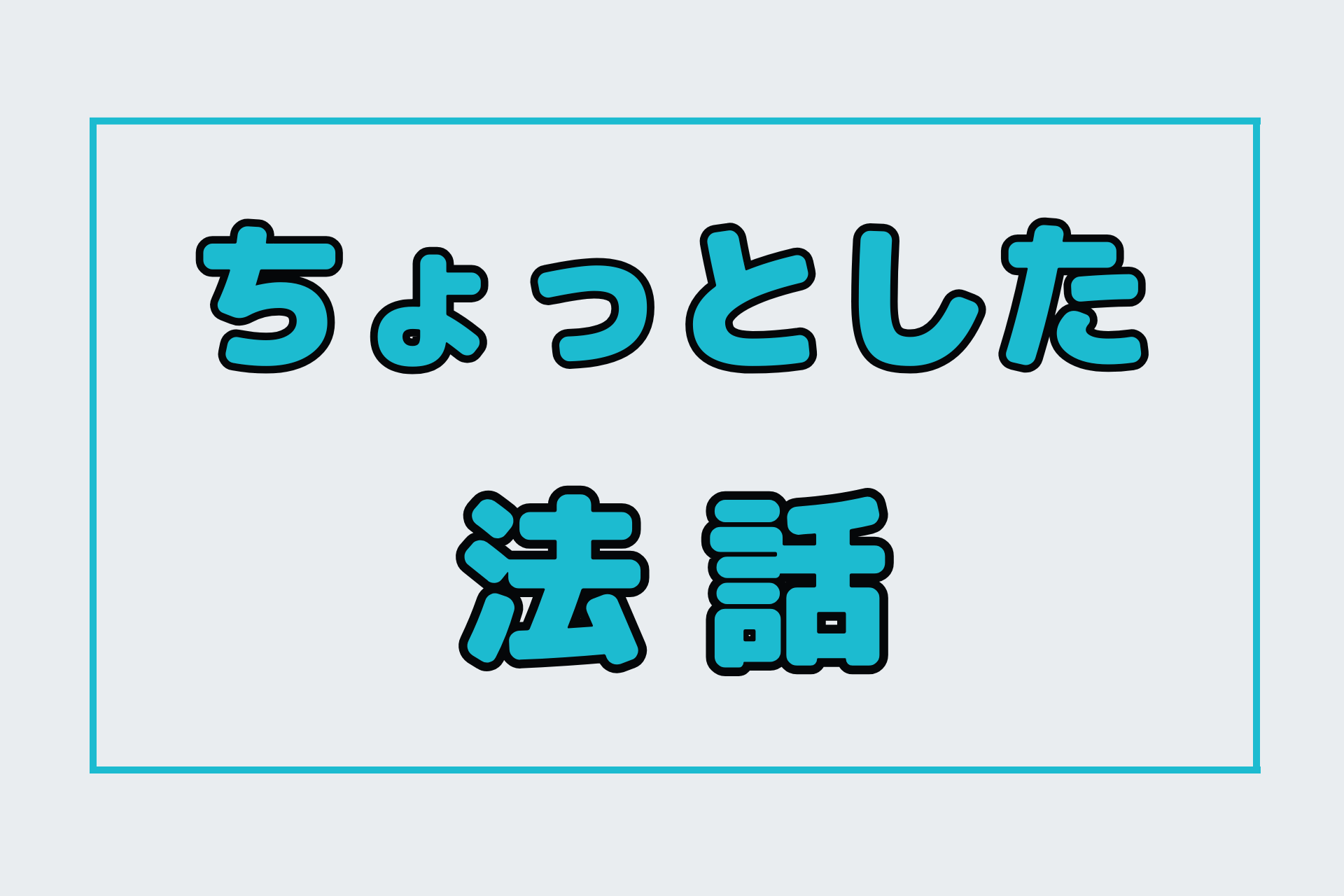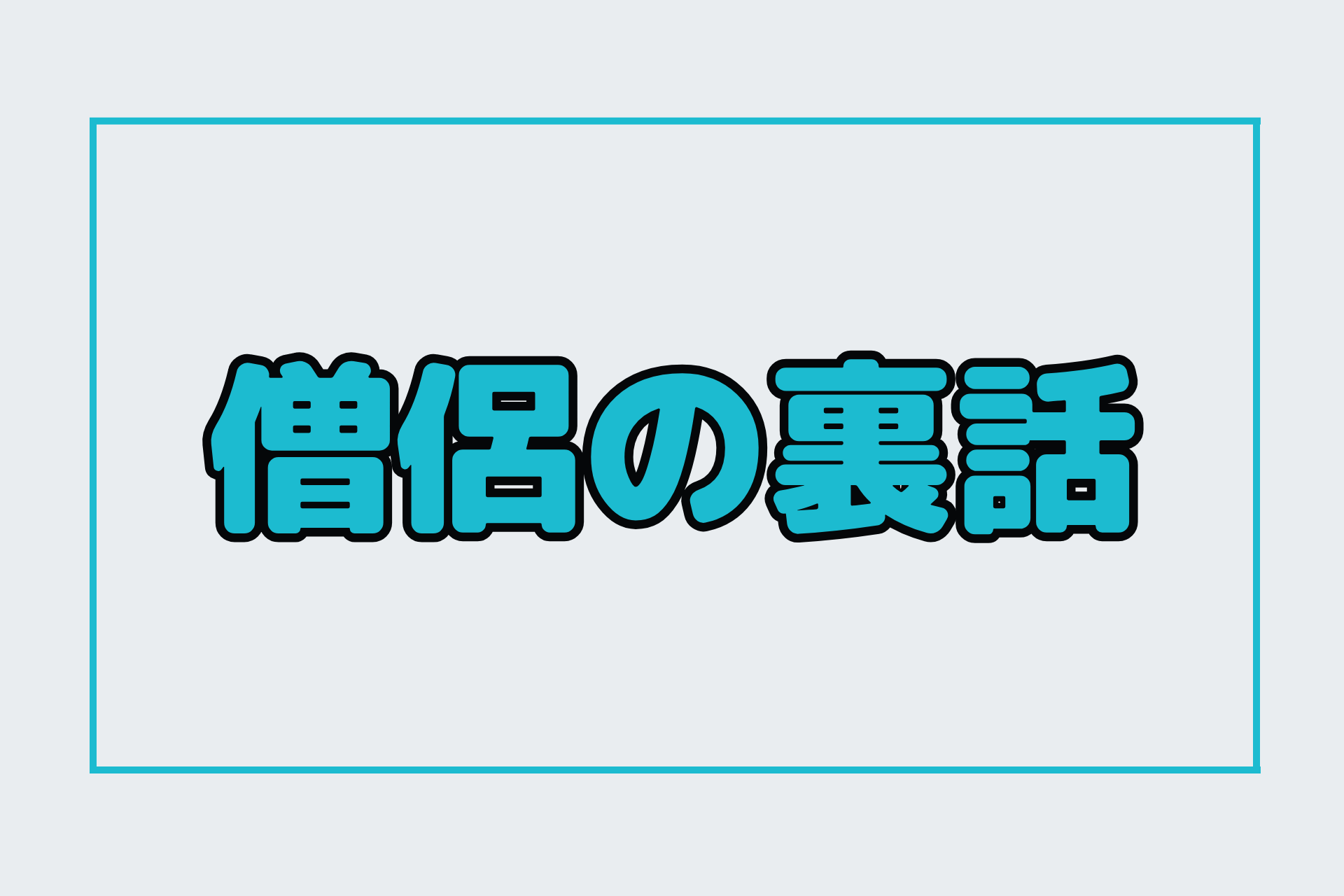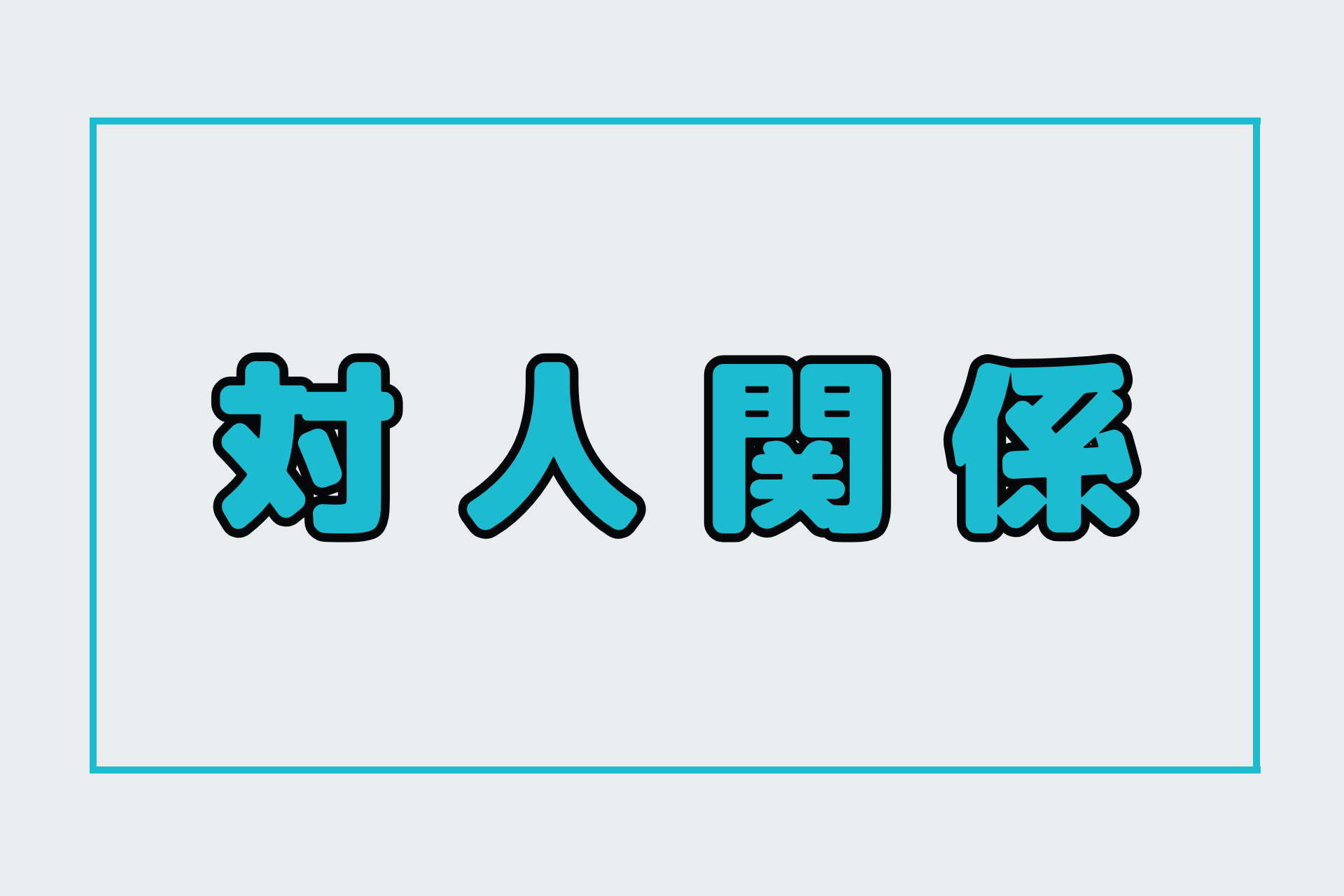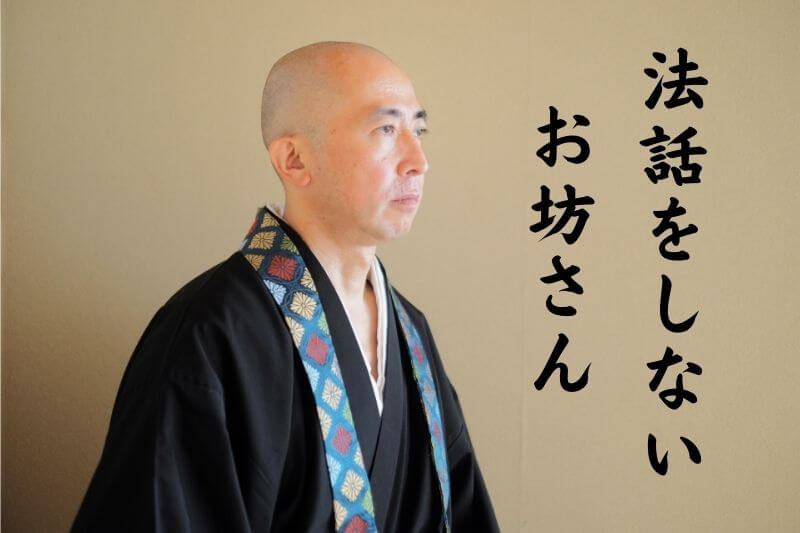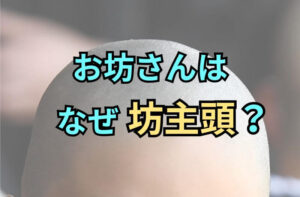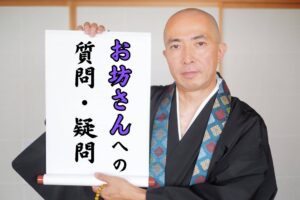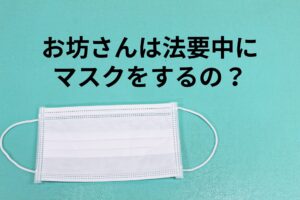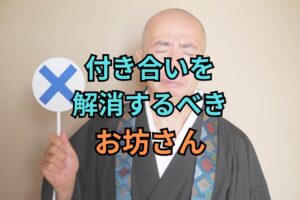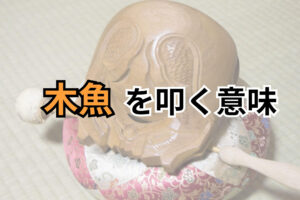- お坊さんが法話をしてくれない理由を知りたい。
- どうすれば法話をしてくれるの?
法事やお葬式のときに、お坊さんがお話(法話)をしてくれないことがありますよね。
何かありがたい話でも聞けるのかと思っていたのに、お経だけで終わってしまうと「えっ、それで終わり?」と不満が残ることでしょう。
法事やお葬式で法話をするのはお坊さんの重要な仕事ですが、残念なことに最近は法話をしないお坊さんが増えています。
お坊さんが法話をしないのには、いくつかの理由があるんですよね。
この記事では、
- 法話に対するお坊さんの考え方
- お坊さんが法話をしない理由
- お坊さんに法話をしてもらう方法
について詳しく解説しています。
お坊さんが『法話』に対してどのように考えているのかが分かりますので、興味のある方は最後まで読んでみてください。
 ちょっき
ちょっき僧侶である私が『お坊さんの事情や本音』を正直にお伝えします!
この記事を書いている私『ちょっき』は、お坊さん歴30年。お坊さんに関する裏話や、人間関係の悩みを解消する内容について発信しています。
お坊さんが法話をする目的
まずは、お坊さんが法話をする目的についてお伝えします。
お坊さんが法話をするのは『仏教の内容を多くの人に知ってもらう』ことが目的です。
そのために、
- 仏様のおっしゃったこと
- 私たちが今ここにいることへの感謝
- 心穏やかに過ごすための考え方
- お唱えしたお経の意味
- 故人とのエピソード
などを【法話】という形で伝えています。
仏教では、私たちが心穏やかに生きるために何を考え、どう行動するべきかを教えていますが、難解な内容も多いんですよね。
そこで、私たちお坊さんが日常的な話題などを例に取り上げながら、できるだけ分かりやすく説明をしていきます。
そして、たくさんの人が参列する法事やお葬式というのは、お坊さんにとって法話をする絶好のチャンスなのです。
でも、じつは、法事やお葬式など【故人を供養するとき】は法話が必要というわけではありません。
故人を供養するときは、お経を読んだり作法をすることの方が重要であり、法話というのは【二の次】なんですよね。
とはいえ、仏教というのは『宗教』です。
宗教は、私たちが安心して、穏やかに、そして豊かに生きていく方法を教えてくれるものです。
だから、供養のときには必要なくても、せっかくたくさんの人がいるなら、そこで仏様の教えを広めなければ非常にもったいないのです。
つい最近お坊さんになったばかりの人ならお経を読むだけで精一杯ですから、その後の法話をする余裕はないでしょう。
しかし、十分な経験があるのに法話をしないお坊さんは、私から言わせると【やる気がないお坊さん】です。
【法話をするお坊さん】と【法話をしないお坊さん】
あるとき、私がいつものように法要を終えたところ、参列者の一人がやって来て、



ここのお寺のお坊さんは【お話】をしてくれるんですね。ありがとうございました。
と言って、そのままお墓参りへ行かれました。



まさか普通に法話をしただけでお礼を言われるとは思いませんでした。
法話をしないお坊さんは意外と多い
法事やお葬式のときでも法話をしないお坊さんは意外と多いです。
お経をすべて読み終わると、「今日はどうもお疲れ様でした。」の一言だけで、その後は特にお話をすることもなく終了してしまうのです。
これだと、お坊さんの法話を楽しみにしていた人にとっては拍子抜けですし、参列者としては話が聞けなかったことへの不満が出てしまいます。
一般的に『お坊さんは法要のときに法話をするもの』というイメージがあると思いますが、それは私たちお坊さんにとっても同じです。



多くのお坊さんは【坊主は法話をしてナンボ】だと思っていますよ。
参列者は、意味の分からないお経を聞いて「あぁ、今日はお経が聞けてよかったなぁ。」なんて思いません。
お坊さんがいろんな話をすれば、参列者に「へぇ、そうだったのか、そんな意味があったのか。」と思ってもらえることもあり、それをちゃんと覚えてくれている人も必ずいるんですよね。
そのようなことが積み重なって、故人の供養の継続に繋がっていきます。
なので、私のように話がヘタでも、お坊さんは頑張って法話をしている方が将来的にもプラスに働くのです。
読経よりも法話の時間が長いお坊さんもいる
法話をしないお坊さんがいる一方で、読経はそこそこにして、大部分の時間を法話に費やすお坊さんもいます。
例えば、霊園ではいろんな宗派のお坊さんが来て供養をしますが、その中には、法要時間の半分以上は法話をしているお坊さんもいるんですよね。
そのようなお坊さんは、お経や作法よりも【仏教をより多くの人に広めること】を重要視しています。



浄土真宗のお坊さんにそのような人が多い印象です。
長時間にわたり法話をするのはとても大変なことです。
なぜなら、
- 豊富な知識
- 飽きさせない話術
が必要だからです。
知識は勉強をした分だけ増えていきますが、問題は話術。
人間は一方的に話を聞くことが苦手で、集中して聞いていられるのは、せいぜい5分くらいです。それなのに、法話はお坊さんが一方的に話すスタイルが主流。
ですから、長時間お話をするためには、
- 飽きない話題(説法の内容)選び
- 引き込む話し方
- ちょっとした笑いの要素
というものがないとダメなんですよね。
法話が長いお坊さんはこれらをやっているわけですから本当にすごいと思います。
しかし、法話の長いお坊さんは1つだけ困ることがあります。
それは、法要の時間が長くなることです。
霊園などでは、一回の法要時間を【30分程度】で収めていただくようお坊さんへお願いすることが多いのですが、法話の長いお坊さんは40分を超えてしまいます。
一生懸命に法話をしていただいて非常にありがたいのですが、次の法事の人たちが来てしまっているので、霊園側は大慌てです。
このように、たくさん法話をしてくれるお坊さんの場合、法要全体の時間が長引く可能性があるので、法要後に食事をする場合は、お店の予約時間に遅れないように気をつけてください。
お坊さんが法話をしない理由
法話をするお坊さんがいれば、法話をしないお坊さんもいます。
では、法話をしないお坊さんは、なぜ仏教を広めるチャンスを放棄してしまうのでしょうか?
人前で話をするのがとても苦手
法話をしないお坊さんの中には、単純に『人前で話をするのがとても苦手』という人がいます。
人前で話すのって、慣れないうちはメチャクチャ緊張しますし、とても恥ずかしいんですよね。



話しているときは『とにかく早くこの状況から解放されたい』という心理になります。
そうすると、自然と早口になって言葉をカミまくり、結果的にうまく話ができません。
でも、数をこなせばそれなりに慣れて話も徐々に上手くなりますから、若い頃からできるだけたくさん法話をして、いろんな経験と失敗をしておいた方がいいのです。
これがもしも、ある程度の貫禄が出る年齢(50歳以降)からお坊さんになった人は大変です。
見た目が【経験豊富なお坊さん】に見えてしまうので、施主や参列者は「いろんな経験をしてきたお坊さんだから、ありがたいお話が聞けるのだろう。」と期待します。



『法話の内容』に対する期待は、お坊さんの年齢が上がるほど大きくなります。
なので、若いうちから法話をしておかないと、年齢を重ねるにつれてプレッシャーが大きくなり、結局は怖くなって話すことをやめてしまいます。
そして、《人前で話すのが苦手》から抜け出せなくなり、その後もずっと法話ができないままです。
あなたが見た『法話をしないお坊さん』は、もしかするとこのタイプなのかもしれませんね。
単なるサボり
お坊さんの中には、話をすることが苦手じゃないのに法話をしないお坊さんがいます。
そういうお坊さんはハッキリ言って単なる【サボり】ですね。
法話をサボっている理由は、法話のネタ作りや勉強が面倒くさいからです。
私たちお坊さんは、法話のネタをある程度の数は用意していますが、数パターンの話だけを使い回すわけにもいきません。
なぜなら、『同じお寺に親戚同士のお墓がある』というケースが多いからです。
例えば、お寺にA家とB家のお墓があり、AB両家は親戚関係であるというケースです。
この場合、A家の法事のときには、親戚であるB家の人たちも参列しています。そのため、A家の法事のときに話した内容は、親戚であるB家の人たちも聞いています。
そして、次にB家の法事のときには、親戚であるA家の人たちも来ます。となると、B家の法事のときには『A家とは違う内容』を話さなければなりません。
しかも、法事は一回だけではありません。
49日忌の次は1周忌、その翌年は3回忌、というように法事は1つの家で何度も行います。
当然ながら、親戚同士の家では法事のたびにお互いに参列し合うので、お坊さんは常に【法話の新ネタ】を考え続ける必要があるんです。



法話のネタを考えるには知識が必要なので、勉強をしなきゃいけないんですよね。
しかし、何となくお坊さんをしている人にとっては、勉強することが面倒くさくて仕方ありません。
そこで、面倒くさがりのお坊さんは【それらしい理由】をつけて、法話をすること、そして勉強することをやめてしまいます。
だから、いつまでたっても法話ができないまま年齢を重ねてしまうんです。
でも、お坊さんの中には『他の仕事もしている』という人が大勢いて、そのようなお坊さん達は本当に忙しいので、法話を考えるあまり時間がありません。



じつは、お坊さんの約70%は他の仕事もしていて、それほどお寺の収入というのは少ないんです。
しかし、他の仕事をしていないお坊さんが法話をしないのは立派な『サボり』です。法話をサボるお坊さんがいるようなお寺は、次第に信者さんが離れていきます。
今はお寺もツブれてしまう時代です、今後そのようなお寺は淘汰されていくことでしょう。
あえて法話をしないケース
普段は法話をしているお坊さんでも、ときにはあえて法話をしない(できない)ケースもあります。
それは、
- お墓の前での法要で、なおかつヒドい悪天候である
- 法事の数が多すぎる
- 火葬までの時間があまりない
というケースです。
供養というのは、必ず『屋根の下』で執り行うとは限りません。
近年ではお墓の前で供養をすることもよくありますが、天候が悪いと大変です。ひどい悪天候のときは法話よりも【参列者を早く解放してあげる】ことを優先する場合があります。
例えば、台風が来ていると本当に悲惨で、強風のため傘がまったく役に立たず、参列者の服は雨でズブ濡れになります。そんな中で普段のように時間を取って法話なんてできません。



ほんの数十秒の【ご挨拶程度のお話】ができればマシな方です。
また、大きな寺院の場合は、法話が省略されがちです。
大きな寺院にはたくさんの信者(檀家)さんがいて、それだけ法事の数も多くなるので、法事1回あたりの時間が短くなってしまいます。そのため、どうしても法話をしている時間がなくなるんですよね。
法事の主な目的は『供養をすること』なので、時間がなければ法話が省略されます。
また、お葬式の後にも法話ができないケースがあります。
お葬式が終わると出棺をし、火葬場へ向かいますが、火葬場というのは非常に時間に厳しく、1分でも遅れると強くお叱りを受けるんです。



場合によっては火葬場での最後のお焼香ができません。
そのため、葬儀式場と火葬場の距離が遠かったり、何らかの理由でお葬式が延びてしまった場合は法話を省略することがあります。
このように、やむを得ない理由により、あえて法話をせずに終わらせることもあるので、そこはどうかお許しください。
法話をしてもらう方法
法話をしないお坊さんでも、中には「やっぱり法話をしないとマズいかな?」と思っている人もいます。というか、サボってるお坊さんは心のどこかでそう思っているはず。
そんなお坊さんには『法話をするきっかけ』を与えてあげればいいのです。
あなただって、せっかくの法事でただお経を聞くだけでは物足りないですよね?あなたの方から少しアクションを起こしてあげるだけで、お坊さんに法話をさせることができるかもしれません。
お坊さんに法話をしてもらうためには、法事の申込みのときに、



恥ずかしながら、仏様のことについてあまり知らないんです。今回の法事でご住職のお話をうかがって勉強させていただきたいと思っています。親戚の者も楽しみにしているみたいなので、よろしくお願いします。
と言いましょう。
お坊さんに対して『もちろん何かお話をしてくれるんでしょ?期待をしてますからね。』という圧をかけておくのです。



つまり『先手を打っておく』ということですね。
これは【法事の申込みのとき】に言うのがいいですよ。
お坊さん側からすると、事前に言ってもらえたら法話のネタを考える時間があるので助かります。それと同時に、法事当日まで時間があるので「出来の悪い法話をするわけにはいかない。」という心理が働きます。
このように、『法話をしてくださいね』ということを先に伝えておくことによって、お坊さんに対して法話をするように促してください。
法話をしないと供養をしなくなる
お坊さんは、供養のときにも法話をするべきです。
意味の分からないお経を聞いたところで、施主や参列者はそこに価値を見出しません。施主や参列者にとっては、良い話を聞けることの方が価値があるんです。
ということは、法話を聞きたいと思ってもらえれば、故人の供養を続けてくれる可能性が上がるだけでなく、仏教のことを知ってもらえる機会も増えます。
それこそが『お坊さんの役目』ですが、その本来の役目を果たさないお坊さんが多いのです。



お坊さんが本来の役目を果たさないから法事をしなくなるんですよね。
お経を読んで終わりというのでは、施主や参列者にとっては何だか物足りないですし、それが毎回続くようだと、供養をしようという気持ちもだんだんと薄れてしまいます。
ただでさえ『宗教離れ』が進んでいる日本ですから、供養をする人が減ってしまうことは、お坊さんにとっては死活問題のはず。
だから、法話をしないお坊さんに対して「下手でもいいから法話をしろ」と言いたい。
その方が、お寺と信者さんの双方にとって良いことだと思います。
まとめ
供養のときに法話をするのは、お坊さんの大事な仕事です。
それをしないお坊さんには、法話をしてもらうようにどんどん要求していきましょう。
特に、法話をサボっているお坊さんには手加減無しでガンガン要求してかまいません。
それは、あなたのためだけではなく、そのお坊さんやお寺にとっても長い目で見れば必要なことです。
ですから、お手間をかけてしまいますが、あなたがそのお坊さんを【育てて】あげてください。
※こちらの記事もよく読まれています。