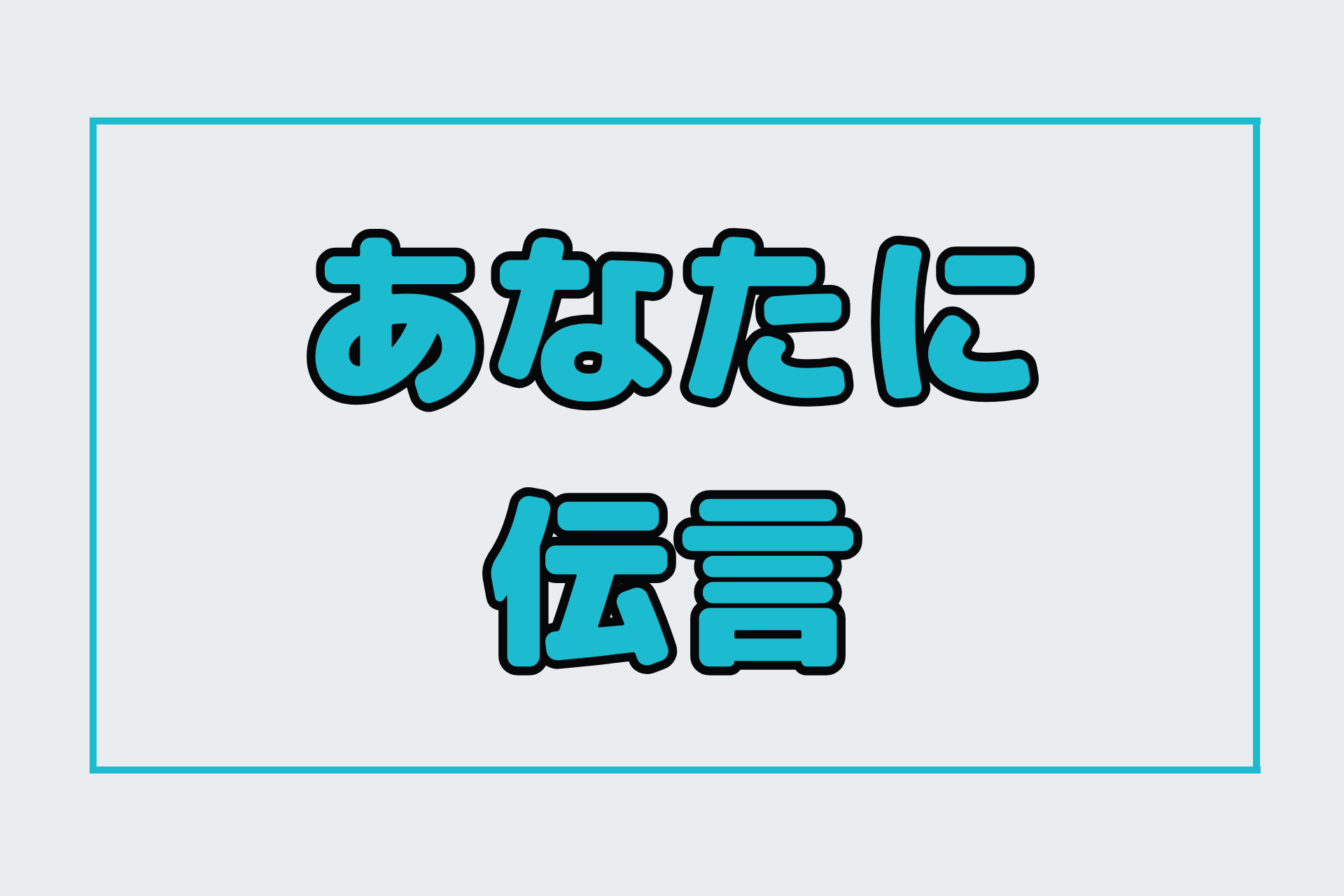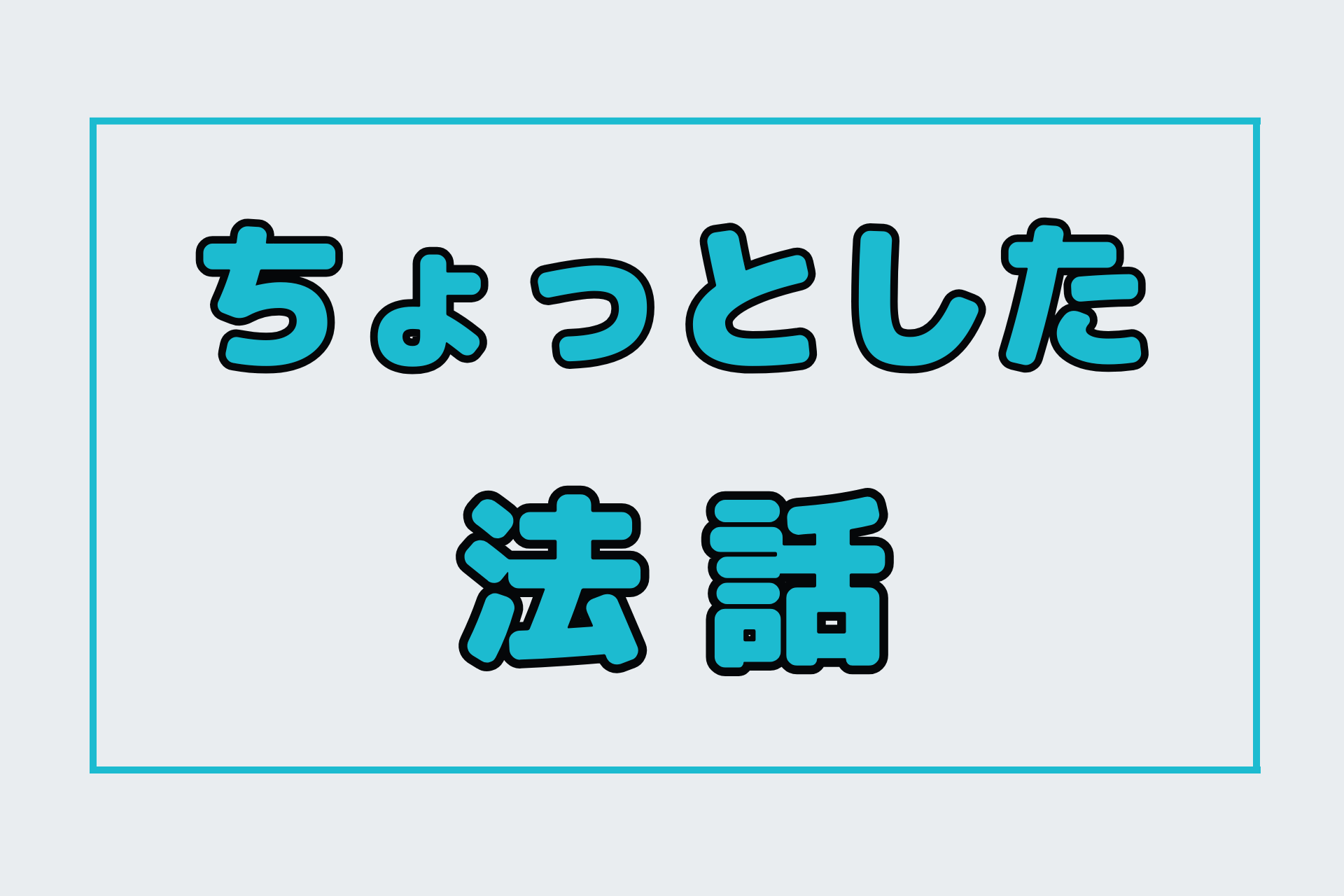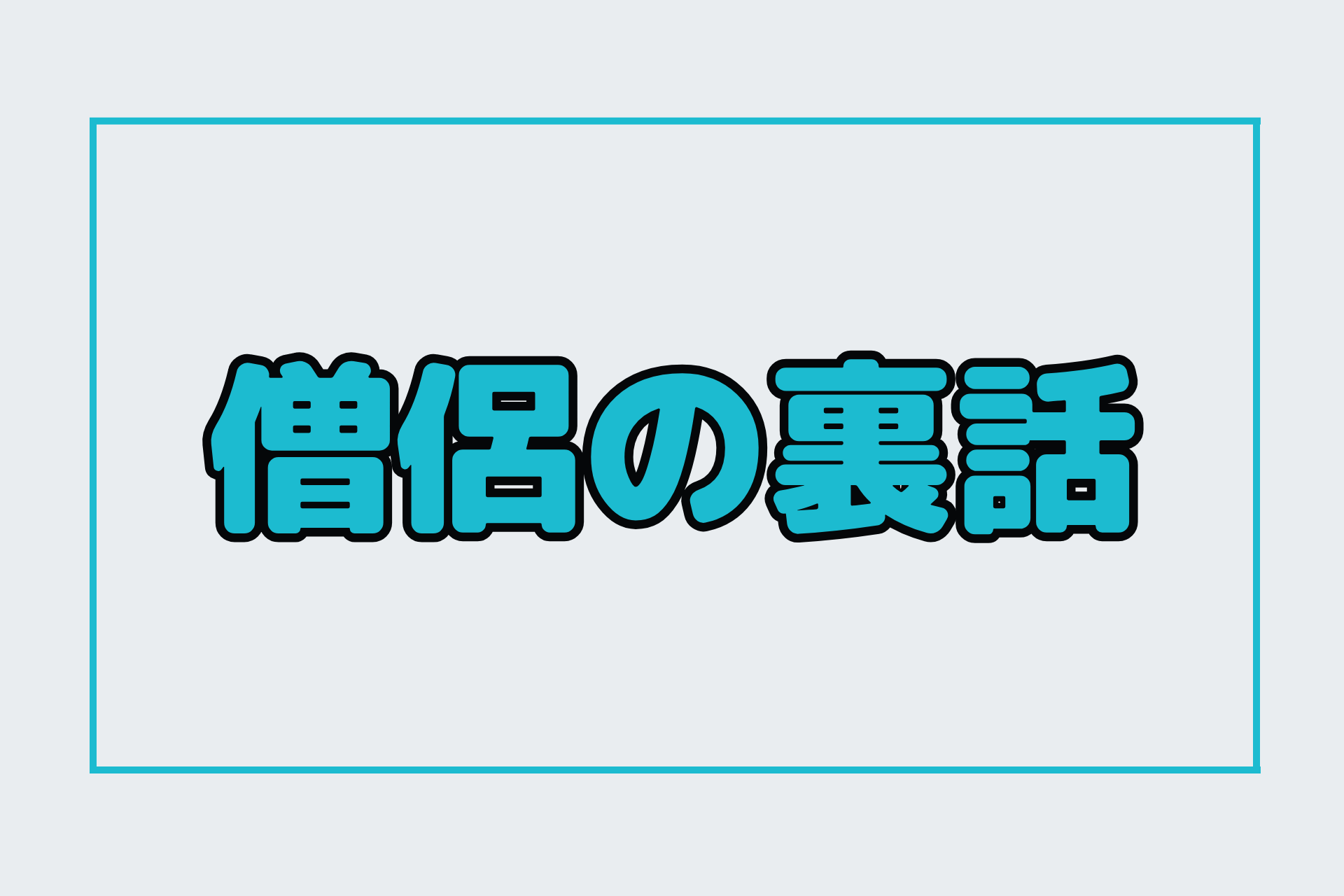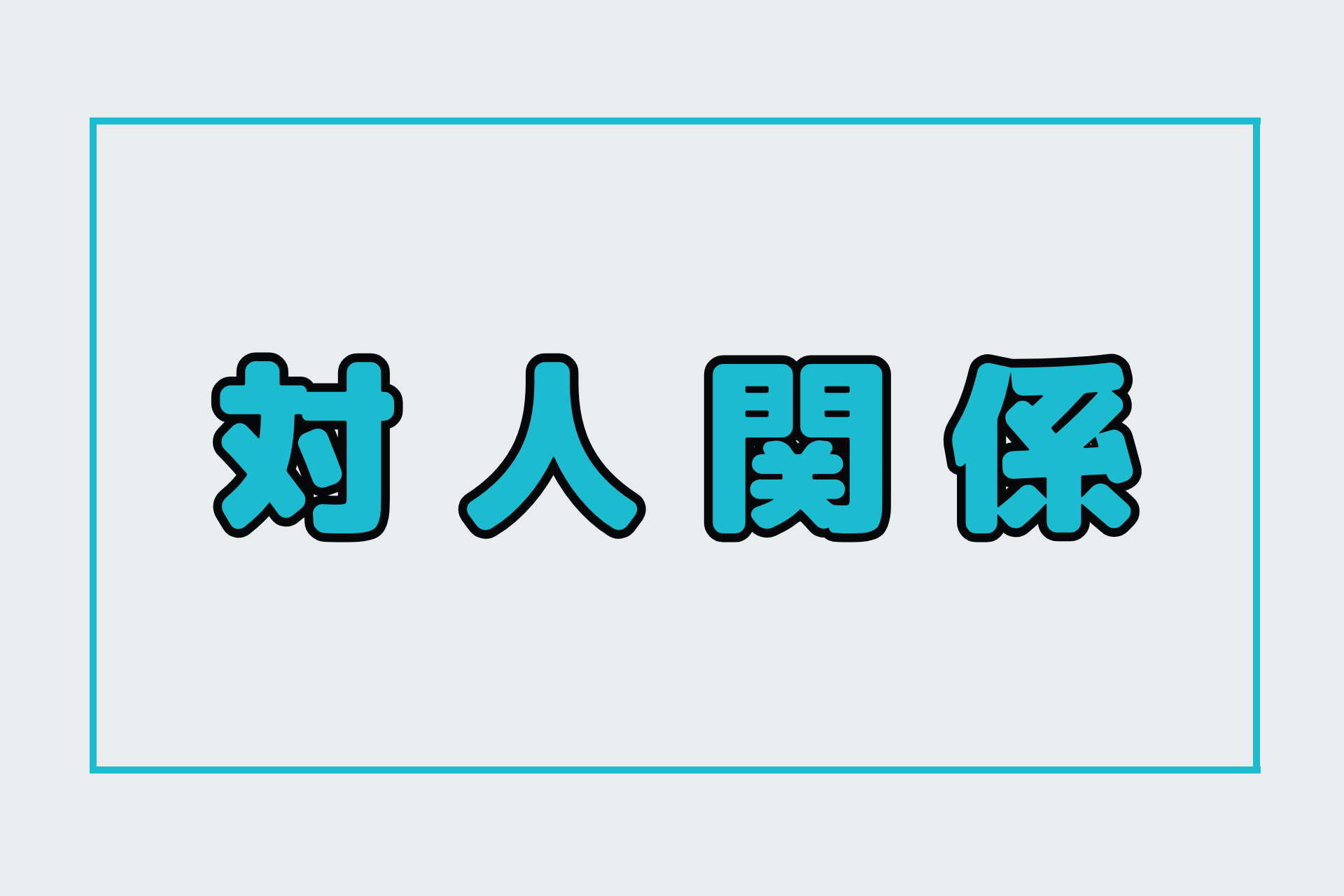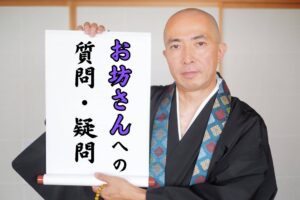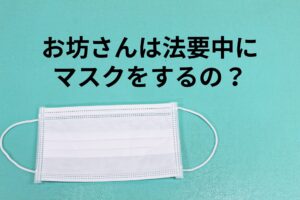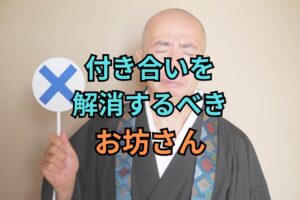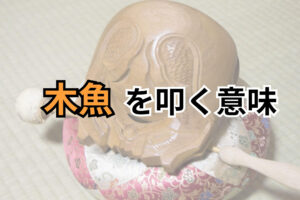あなたは「お坊さんはお金持ち」というイメージがありませんか?
お坊さんといえば、高級車を乗り回し、美味しいものを食べ、それでも生活に困らない人のように思いますよね?
しかし、じつはお坊さんの多くが【他の仕事をしないと生活できない状況】なのです。
そのため、お坊さんの収入源はお寺以外にもいろいろあります。
この記事では、現役僧侶の私が『お坊さんのお金事情』について紹介しています。
最後まで読んでいただき、少しでもお坊さんの現状を知ってもらえれば幸いです。
この記事を書いている私『ちょっき』は、お坊さん歴30年。お坊さんに関する裏話や、人間関係の悩みを解消する内容について発信しています。
お坊さんの収入源は何?
お坊さんの収入源はいろいろあります。
というか、お坊さんの仕事だけでは到底生活ができませんので、他の仕事もしなくてはいけないのです。
では、具体的にお坊さんの収入源には何があるのでしょうか?
お寺からの給料
お坊さんの収入源の基本はお寺からの給料です。
お坊さんは、お葬式や法事などの宗教行為をすることで、檀家さんや信者さんから『お布施』を頂きます。
その頂いた『お布施』が全部お坊さんの収入になる・・・ことはありません。
頂いた『お布施』はすべて一旦《お寺》に入ります。
宗教行為をしたのはお坊さんでも、それにより得たものは全部《お寺》のものなんです。
それらの『お寺の収入』の中から、お坊さん個人に対して【給料】が支払われます。
ですから、お寺の収入が少なければ、それだけお坊さん個人の収入も少なくなるということです。
そして、お坊さんの給料を安定的に支払えるようなお寺というのは少数で、その数もどんどん減っています。
そのため、お坊さんは他の仕事をせざるを得ない状況になっているのです。
他の仕事からの収入
お寺の収入が少ない以上、お坊さんは他の仕事からの収入を得なくてはいけません。
では、お坊さんたちは他にどのような収入源を持っているのでしょうか?
他の職場からの給料
お坊さんは、お寺ではない他の職場に勤務している人も大勢います。
特に多いのは『学校の教師』で、お坊さんの知識を活かせる《国語》や《歴史》の教師になる人が多いです。
また、学校は基本的に土日祝日が休みであり、そこで法事などが行えるので、学校の教師はお坊さんの仕事と両立させるには最適なのです。
もちろん、教師以外の職に就くお坊さんもたくさんいますが、土日祝日の休みのときに法事をしています。
ただし、お葬式については土日祝日が関係ないので、臨時に休暇をとって執り行うことが多くなります。
保育園や幼稚園の運営
お寺によっては、保育園や幼稚園を運営しているところも多いです。
お寺で運営している保育園や幼稚園というのは、法人税や消費税などが非課税となります。
お寺で行う事業は、そこに布教など宗教活動の目的があれば公共事業としてみなされ非課税となるのです。
そのため、お寺が運営している保育園や幼稚園では、子どもたちの保育や教育において仏教的な要素が取り入れられています。
ですから、そのような園に通う子どもたちは簡単なお経ならお唱えできます。
お寺による保育園や幼稚園の運営は公共事業ではありますが、いくらかの収入にはなりますので、それがお坊さんの収入源の1つとなるのです。
講演料
お坊さんというのは、仏教を専門とする『宗教者』です。
宗教者の仕事は、多くの人々に教えを広めること、要するに【布教】です。
布教の方法として一般的なのは説法(説教)ですが、説法が得意なお坊さんは講演をすることもあります。
特に、多くのメディアに紹介されているようなお坊さんの場合、講演の回数も多く、講演料も高額となります。
ですから、説法が得意なお坊さんにとっては講演料が収入源の1つとなるのです。
本の出版による収入
たくさん講演をしているお坊さんには、本の出版の依頼が来たりします。
本の出版をすれば相応の原稿料や印税がもらえます。
もしも、その本がメディアに取り上げられて話題になれば、さらに講演の依頼が来たりするのです。
それがまた新たな本の出版に繋がり、布教の範囲をどんどん広げていきます。
このように、説法が得意なお坊さんは、僧侶としてだけではなく、作家としても優秀であるといえます。
貸地の収入
ずっと昔、お寺の土地というのは広大でした。
その後、お寺の土地を貸し出すことが増えていき、それが現在でも続いています。
例えば、
- 駐車場
- 店舗
- 住宅地
- 商業施設
- 農地
など、お寺の貸地はたくさんあります。
そして、このような貸地の地代が大事な収入となっているお寺も多いです。
宿泊料
お寺によっては、一般の方々が宿泊できるようにしています。
よく『修行の体験ができるお寺』がありますが、そのようなお寺では参加者が宿坊(宿泊所)に泊まります。
そのような宿泊施設があるお寺にとっては宿泊料も大事な収入です。
しかし、宿坊があるのは比較的大きいお寺だけなので、すべてのお坊さんが得られる収入ではありません。
自動販売機の販売手数料
宿泊施設があるような大きなお寺には、飲料の自動販売機が設置されているところが多いです。
また、観光客を主に受け入れているお寺にも自動販売機が必要です。
ちなみに、自動販売機はどこのお寺でも設置できるわけではありません。
飲料メーカーが定めた《集客数の基準》をクリアできそうな場所にしか設置できないのです。
とはいえ、自動販売機の販売手数料というのはそれほど大きな金額にはならないので、収入よりも参拝客の利便性のために設置しています。
線香・ろうそく・生花・数珠などの販売による収入
お墓参りをするときには、線香、生花、ろうそくなどを使用しますよね。
多くの人はこれらを自分で用意しますが、遠方から来た人や、自宅の近くに生花店がない人はそれができないこともあります。
そこで、参拝者のために線香、生花、ろうそくなどを販売しているお寺もあります。
そして、これらの販売によって、お寺側もいくらかは収入を得ることができるのです。
お寺やお坊さんは税金を払っています
お坊さんはいろんな収入源を持っています。
そして、お坊さん個人の収入はちゃんと課税されています。
世間では「お坊さんの収入はすべて非課税だからズルい。」と思っている人がいますが、それは間違いです。
非課税の対象となるのは【宗教行為による収入】のみです。
そして、お坊さんの宗教行為によって得られた収入はすべて『お寺の収入』となります。
つまり、非課税となるのはお寺の収入だけで、お寺から給料をもらっているお坊さん個人の収入は課税対象なのです。
ですから、お坊さんは、みなさんと同じ条件で納税をしています。
また、宗教行為以外で得られた収入については、もちろん課税されています。
本記事でこれまで紹介してきた【お坊さんの収入源】の中には宗教行為ではないものがたくさんありますが、それらはすべて課税対象なのです。
お坊さん個人としては『税金免除で坊主丸儲け』なんていうことはあり得ませんので、その点は誤解のないようにお願いします。
《関連記事》:お坊さんは税金を払わない?税金免除で坊主丸儲けって、そんなワケないでしょ!
まとめ
多くのお坊さんは、お寺からの給料だけでは生活ができません。
そのため、お坊さんはいろんな収入源を持っています。
そして、それらの収入のほとんどが課税対象となっており、お寺からの給料も含めてお坊さん個人が税金免除になることはありません。
本記事で紹介した【お坊さんのお金事情】について少しでもご理解をいただければ嬉しく思います。
※お坊さんに関する疑問についてはコチラの記事を読んでみてください。