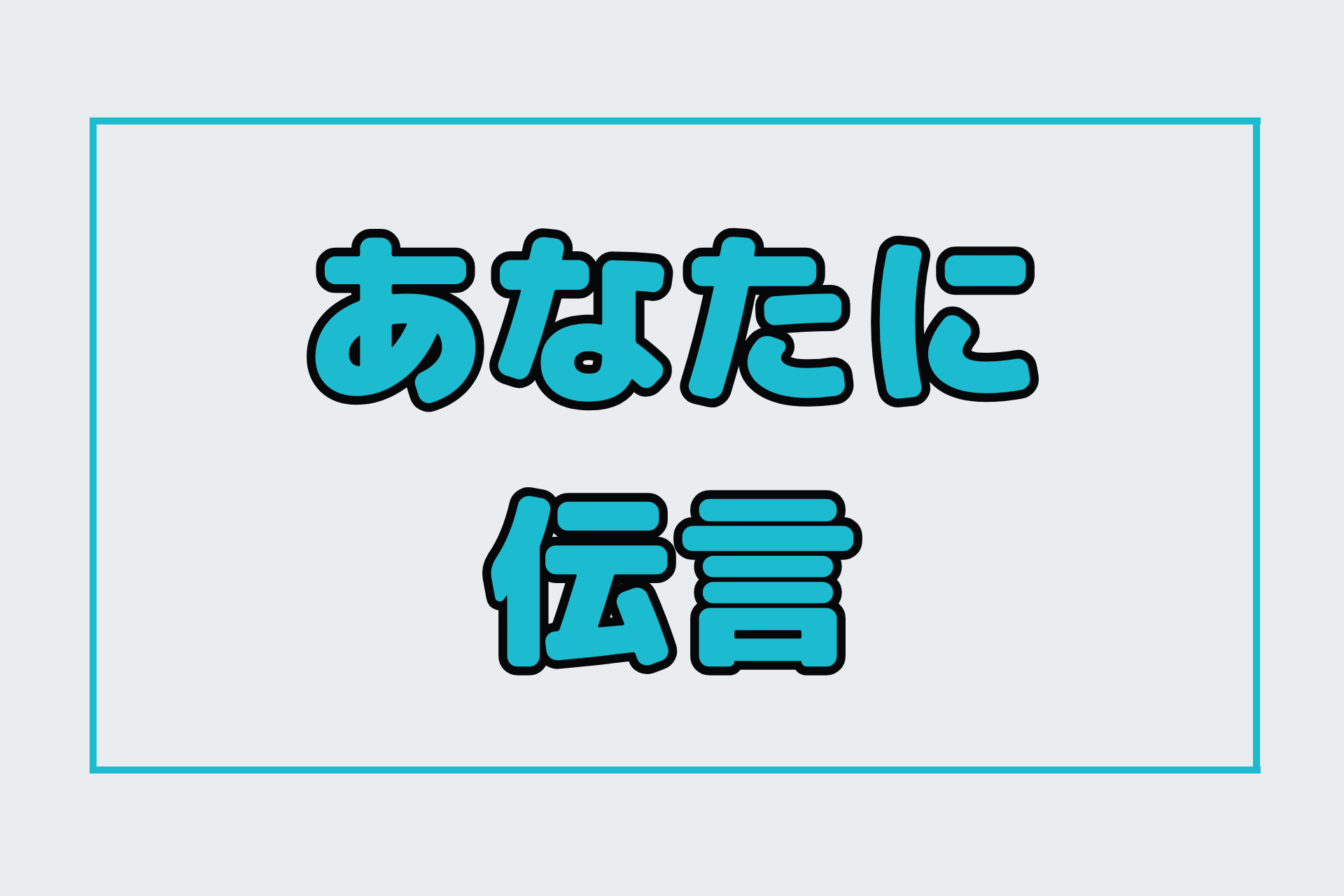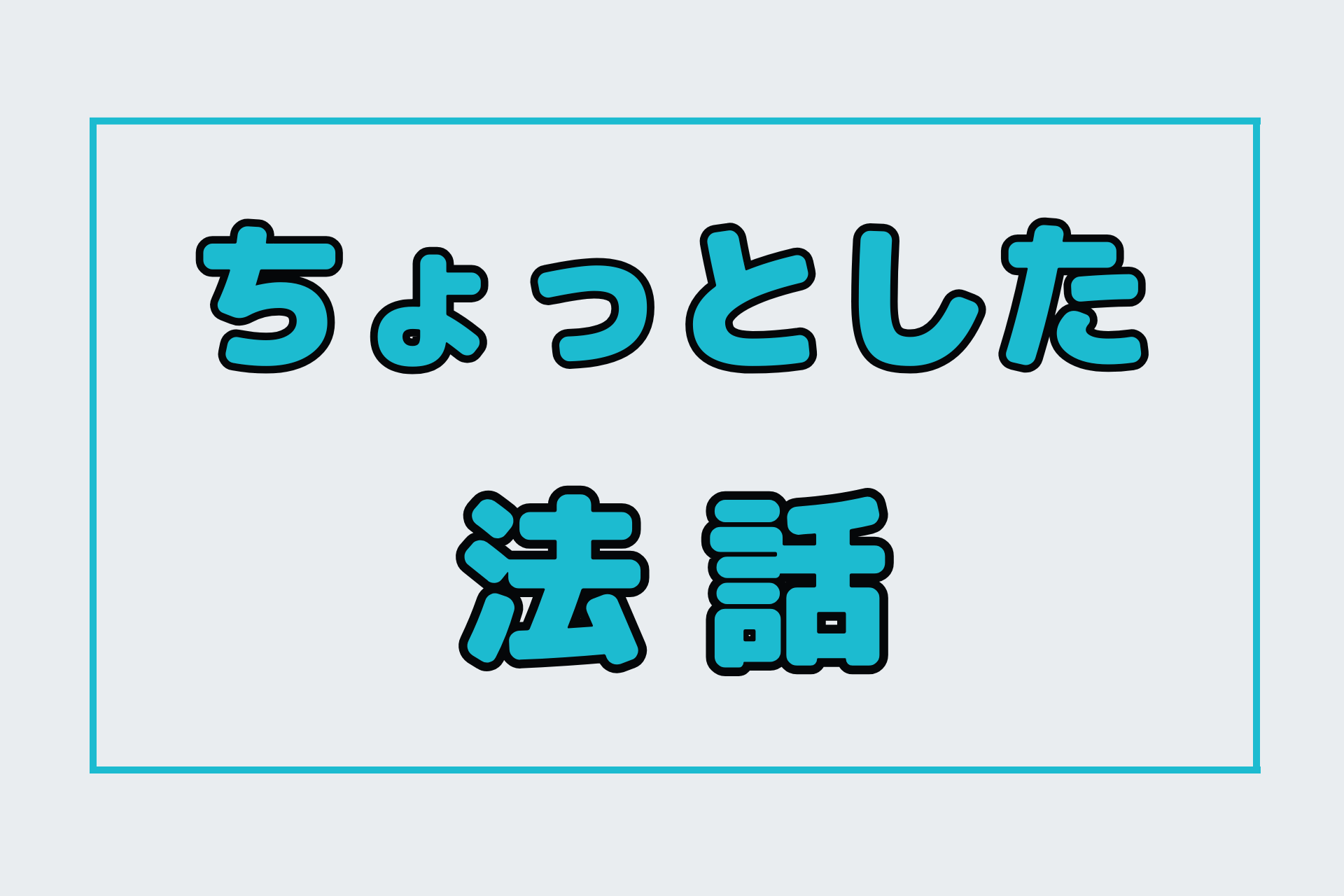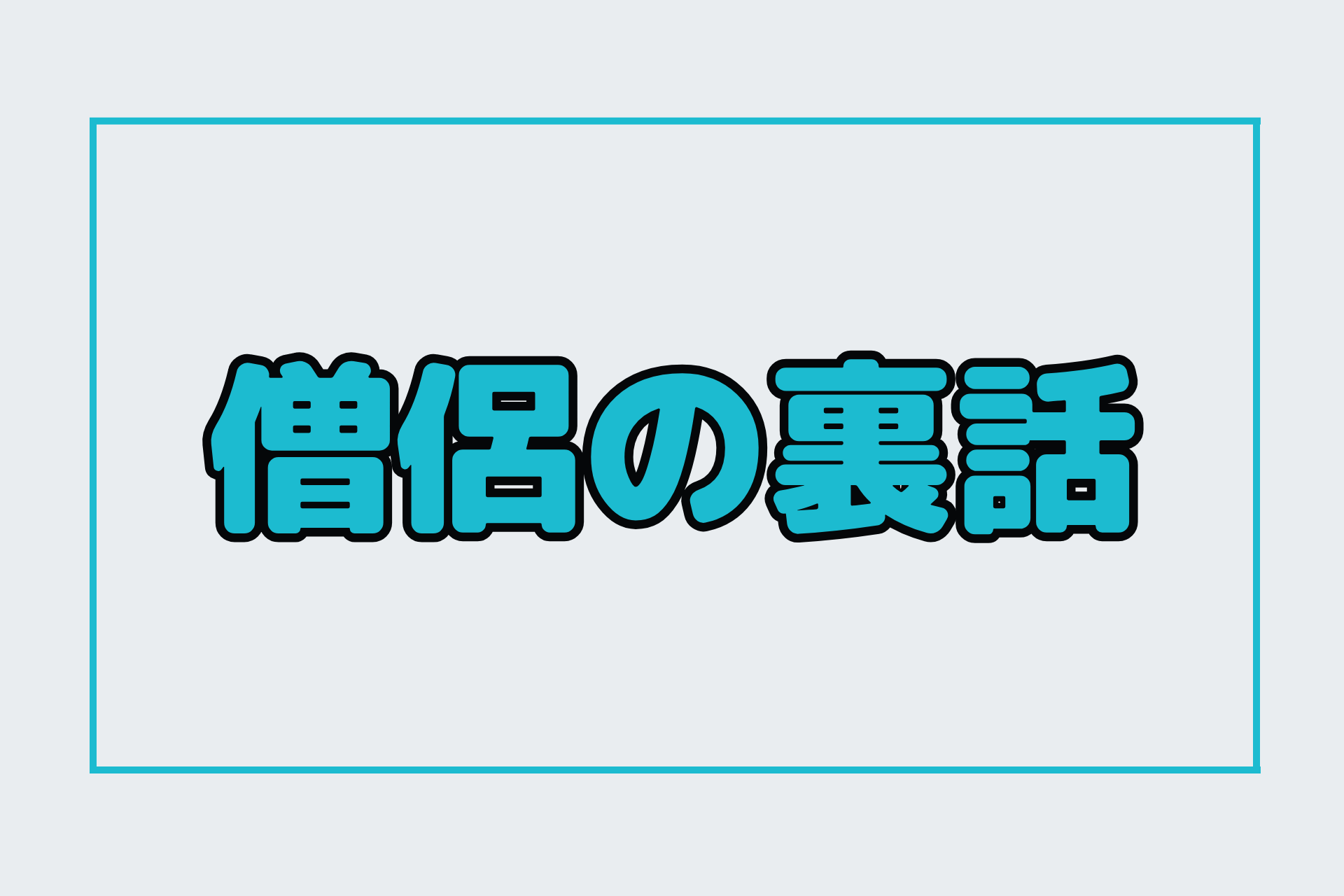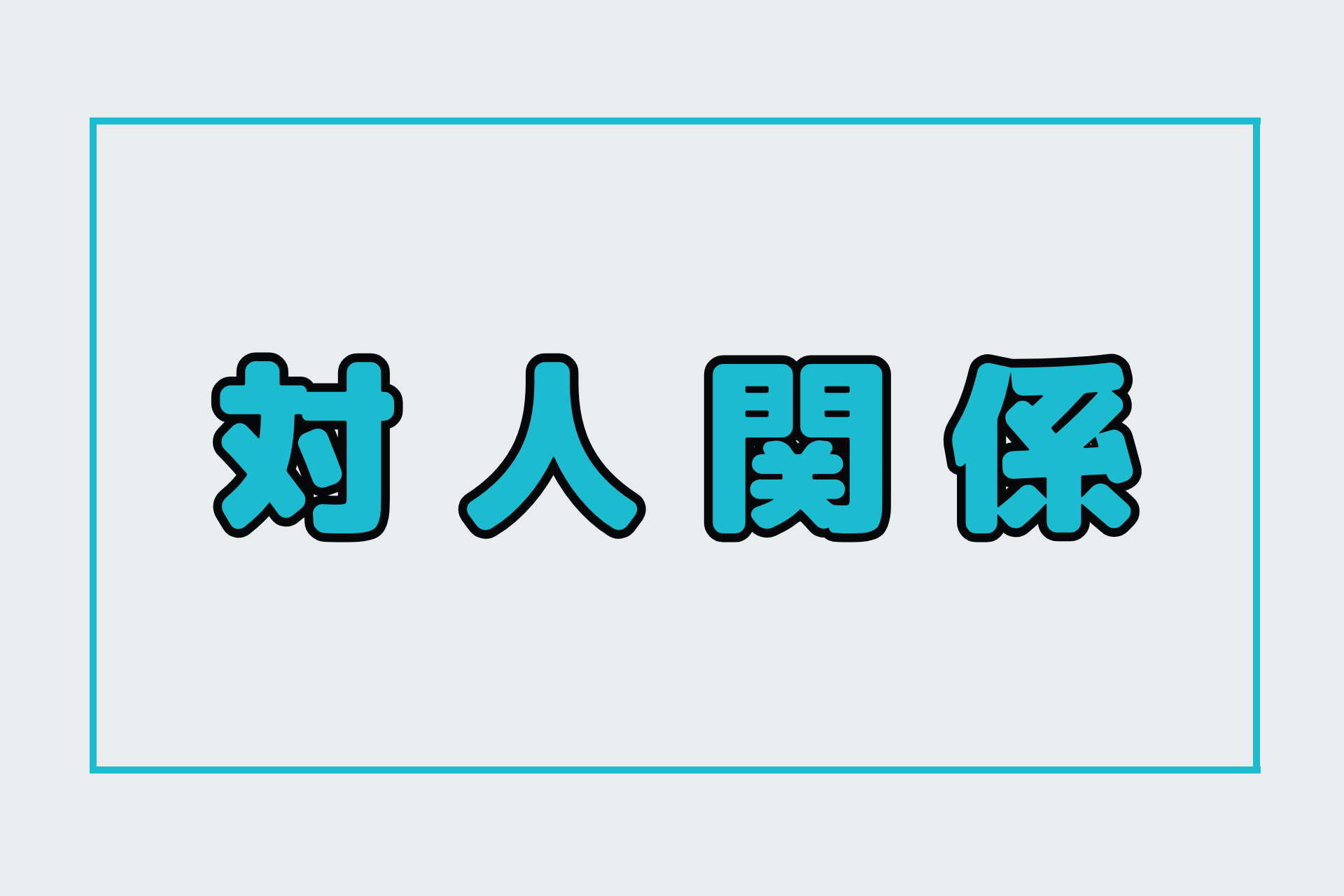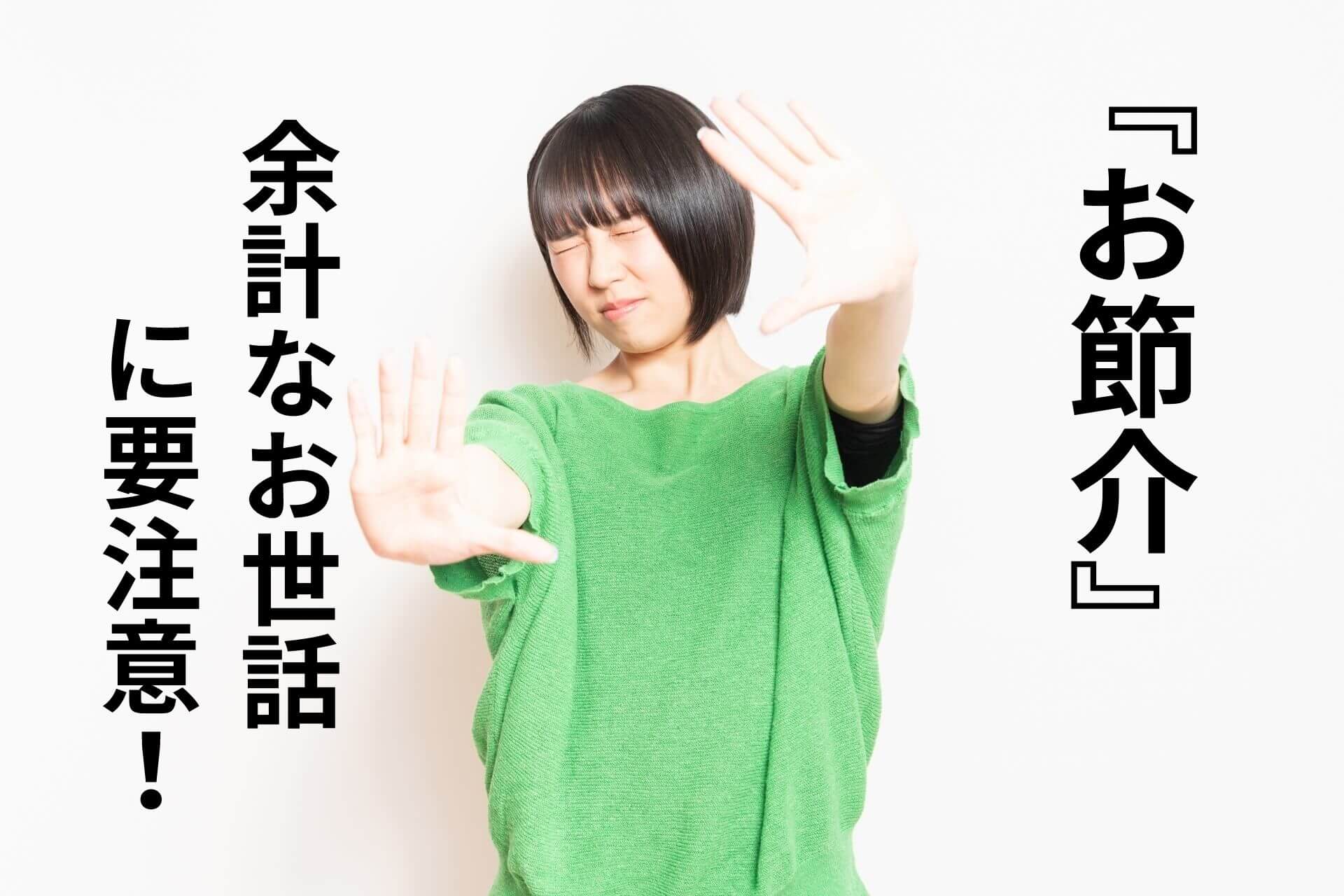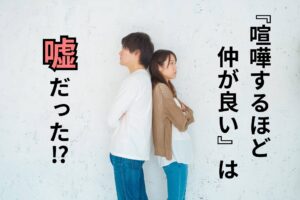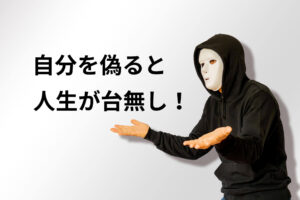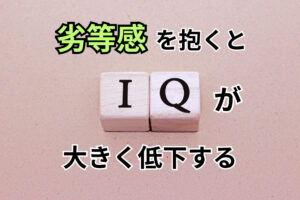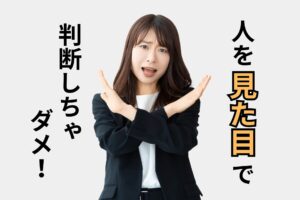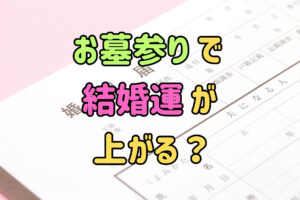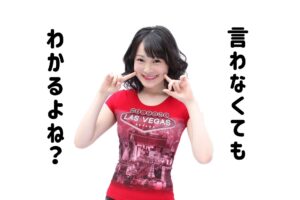目の前に困っている人がいたら、「何か手伝ってあげようかな。」と思いませんか?
手助けをして相手が喜んでくれると嬉しくなりますよね。
でも、正しい方法で手助けをしないと『余計なお世話』になり、かえって相手に迷惑をかけてしまいます。
じつは、手助けをするときにはちょっとしたコツがあるんですよね。
そこで、この記事では【相手に喜ばれる手助け】について解説しています。
あなたの親切が無駄になってしまわないよう最後まで読んでみてください。
 ちょっき
ちょっき『お節介』には気をつけましょう。
この記事を書いている私『ちょっき』は、お坊さん歴30年。お坊さんに関する裏話や、人間関係の悩みを解消する内容について発信しています。
他人を助けるのは良いこと
目の前に困っている人がいたら、手を貸してあげたくなりますよね。
他人を助けるのはとても良いことなので、困っている人を見かけたらぜひ助けてあげてください。
助けてもらった側は、負担を軽減できるだけでなく、早く問題を解決できることで時間を有効に使えるので本当にありがたいですよね。
また、助けた側の人も『ヘルパーズハイ』と呼ばれる状態となり、人を助けることによって自身の幸福感が増すという研究結果も出ています。
ですから、人助けをすると、助けられた側と助けた側のお互いにとってメリットがあるのです。
ただし、お互いにメリットがあるのは、まず相手から助けを求められて、それから手助けをしたという場合です。
じつは、助けを求められていないのに自分から先に手助けをすると、助けられた側と助けた側のお互いにとってデメリットとなってしまいます。
いわゆる『余計なお世話』や『いらぬお節介』ですね。
自分から先に手を差し伸べるのではなく、相手が出した《救いを求める手》をしっかりと握ってあげるのが正しい人助けとなります。
あなたの手助けは【余計なお世話】かもしれない
人助けをするときには、正しく手助けをしないと相手に迷惑をかけてしまいます。
2018年にミシガン州立大学の研究で、いろんな職業や年齢層の人を対象に、人助けをすると《助ける側》と《助けられる側》でどのような心理的な違いがあるのかを調べたものがありました。
すると、相手から頼まれる前に手助けをすると、助ける側と助けられる側の双方にとってメリットが無いことが分かったのです。
自分から先に手助けをすると相手に喜ばれない
人助けをする場合、自分から先に手助けをすると相手に喜ばれない可能性があります。
なぜなら、あなたは助けてあげたいと思っていても、相手がそれを望んでいないかもしれないからです。
自分が大変なときに誰かが助けてくれたら嬉しいですよね。だから、困っていそうな人がいたら、率先して助けてあげようと思うことは自然なことです。
しかし、あなたの親切心が、相手にとっては【余計なお世話】になる可能性があります。
あなたが気を利かせて手助けを申し出ると、おそらく相手の人は「ありがとうございます、では○○をお願いします。」と言うでしょう。
でもそれは、せっかく手助けを申し出てくれたあなたの気分を害さないように、あえて手伝ってもらっただけです。
相手に喜んでもらえてこそ本当の人助けになります。
自分から先に手助けをすると相手の自尊心を傷つける
助けを求められる前に自分から先に手助けをすると相手の自尊心を傷つけることになります。
もしかすると、相手の人は自分で困難を乗り越えようと頑張っているかもしれませんよ。
それなのに、こちらから先に「何か手伝いましょうか?」と言ってしまうと、相手のやる気を削いでしまいます。
さらに、相手の人は「もしかして自分は《力量不足》だと思われているのかな?」と感じるかもしれません。
あなたは良かれと思って手助けを申し出ても、相手の人は『自分は低く評価されている』と思ってしまう可能性があるんです。
なので、手助けをするときには、うかつに声をかけず、相手の人の自尊心にも十分に配慮しましょう。
手助けをした側も良い気分にはなれない
相手から求められる前に手助けをすると、じつは、手助けをした側も良い気分にはなれないのです。
相手の人は、自分が頼んでいないのに手助けをされたわけですから、助けられたことに対してほとんど感謝の気持ちはありません。
もっと言うと、手助けされたことを【迷惑】に思っているかもしれません。
いわゆる『いらぬお節介』ということです。
そのため、助けた側の想像するような良いリアクションではなく、ぶっきらぼうな薄いリアクションが返ってきます。
すると、助けた側は相手に喜んでもらえなかったことで、
- なぜ感謝してくれないのだろう?
- 役に立てなかったのかな?
- 手助けなんかしなきゃよかった。
という不満が残ります。
このように、場合によっては手助けした側も良い気分になれないことがあるので人助けは難しいんですよね。
『相手に喜ばれる手助け』をする方法
せっかく人助けをするなら『相手に喜ばれる手助け』をしたいですよね。
手助けをするには少しコツがありますので紹介します。
相手の人に助けを求められてから手助けをする
手助けをするなら、必ず『相手の人に助けを求められてから』にしてください。
先述したように、良かれと思って先に手助けをすると、お互いに気分を害する可能性があります。
だから、相手の人に助けを求められるまでは手助けをせずに、助けたい気持ちをグッと抑えてください。
そして、相手の人が「すみません、少し手伝っていただけませんか?」と頼んできたら快く受けてあげましょう。
ちなみに、何も言わずに助けを待っている『察してちゃん』タイプの人もいます。
しかし、『察してちゃん』は他人を利用しようとしているだけなので手助けをする必要はありません。
《関連記事》:非常にうざい『察してちゃん』の特徴と心理。シンプルで具体的な対処法を紹介
あなたが5分以内に解決できる得意分野で手助けをする
助けを求められた場合、何でも引き受けるのは賢明ではありません。
助けを求められたら、『あなたが5分以内で解決できる得意分野』で手伝ってください。
時間は有限で、すべての人に平等に与えられています。
人助けをするには《あなたの時間》を使いますので、あまり長時間を費やすのは好ましくありません。
それに、助けを求めた側も、あなたに負担をかけすぎると罪悪感が大きくなってしまいます。
とはいえ、5分というと「そんな短時間じゃ相手の助けにならないのでは?」と思うかもしれませんね。
しかし、あなたは5分以内で解決できる問題でも、相手の人にとってはその何倍もの時間と労力が必要なのです。
だから、あなたの得意分野なら5分以内でも十分な助けになります。
しかも、5分以内くらいであれば、《手助けする側》と《手助けされる側》の両者にとって精神的な負担が少なくすむんですよね。
また、人間には【手助けをした人に対して好意的になる】という面白い心理が働くので、以後のお互いの関係も良くなります。
というわけで、手助けをする側もされる側もあまり負担のないように、ある程度お互いに割り切って協力し合うのがベストです。
いつでも助けられることを伝えておく
あなたの周囲の人には『いつでも助けられることを伝えておく』といいですよ。
前もって「何かあれば手伝うから言ってね。」と伝えておけば、いざというときにお互いに頼みやすいですよね。
他人に助けてもらうのは少し気が引けるものなので、いつでも助け合えるように、日頃からお互いに頼みごとをするハードルを下げておきましょう。
親切な老人と修行僧の話
親切にすることが必ずしも他人のためになるとは限りません。
仏教にはこんな話があります。
ある村にとても親切な老人がおりました。
その老人は、困っている人を見ると、すぐに自分から手助けをします。
ある日、村に1人の修行僧がやって来て、大きな木の陰で眠っていました。
修行僧は、あばらが浮き出て、可哀想なくらいに痩せていたので、老人は「このままでは飢えて倒れてしまう。」と思い、修行僧の足元にそっと食べ物を置きました。
しかし、目を覚まして食べ物を見つけた修行僧は、「これはありがたい。しかし私には不要だ。」と言って、腹を空かせている村人に食べ物をすべて与えたのです。
じつは、修行僧は【断食】をしており、そのせいで痩せていたのでした。
この話は、たとえ善意であっても物事を《自分の目線》だけで見てはいけないことを教えています。
まとめ
手助けをするのは、必ず【相手に助けを求められてから】にしましょう。
相手に求められる前に手助けをすると、相手の自尊心を傷つけ、手助けをした側も不満が残る結果となりやすいです。
そして、助けを求められたら『あなたの得意分野で5分以内に解決できること』で手助けをしてください。
誰かに助けを求めるのは少し気が引けるものですが、日頃から協力し合える関係になっていれば、いざというときに安心して頼ることができます。
あなたもいつ誰かの助けが必要になるか分かりません。
今のうちから周囲の人たちに「何かあれば手伝うから言ってね。」と伝え、いつでもお互いに頼ることができる良好な人間関係を築いておきましょう。
※こちらの記事も読まれています