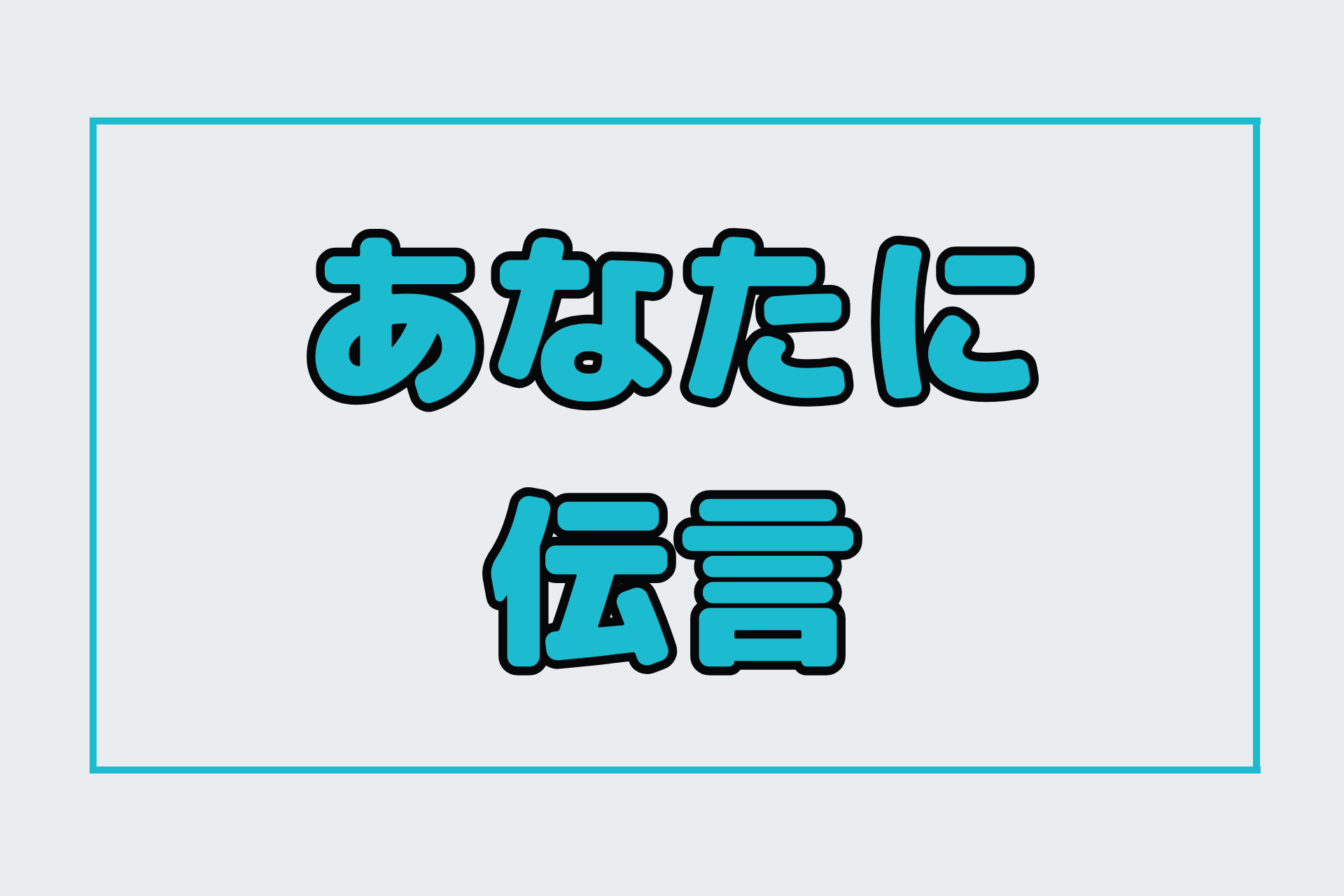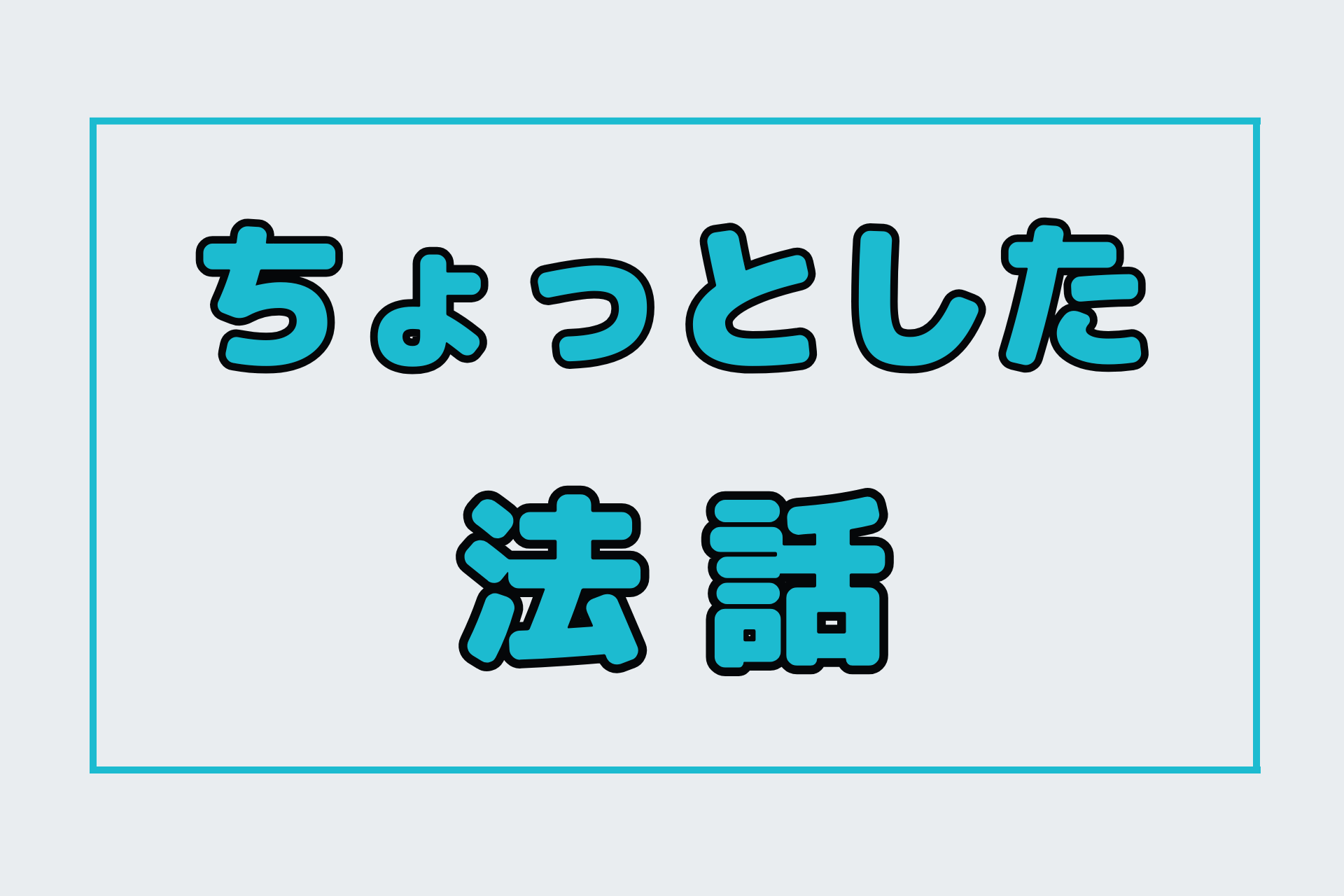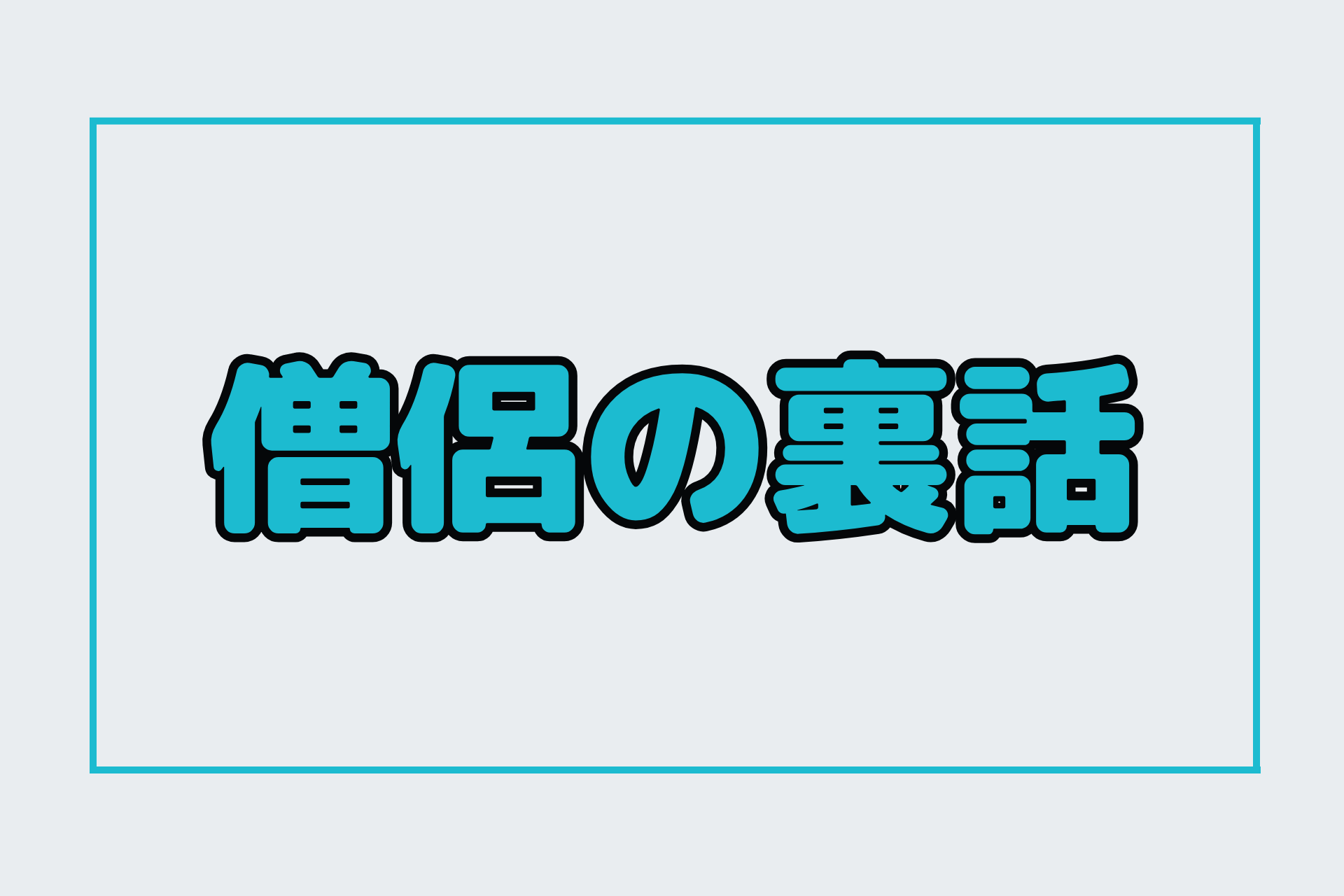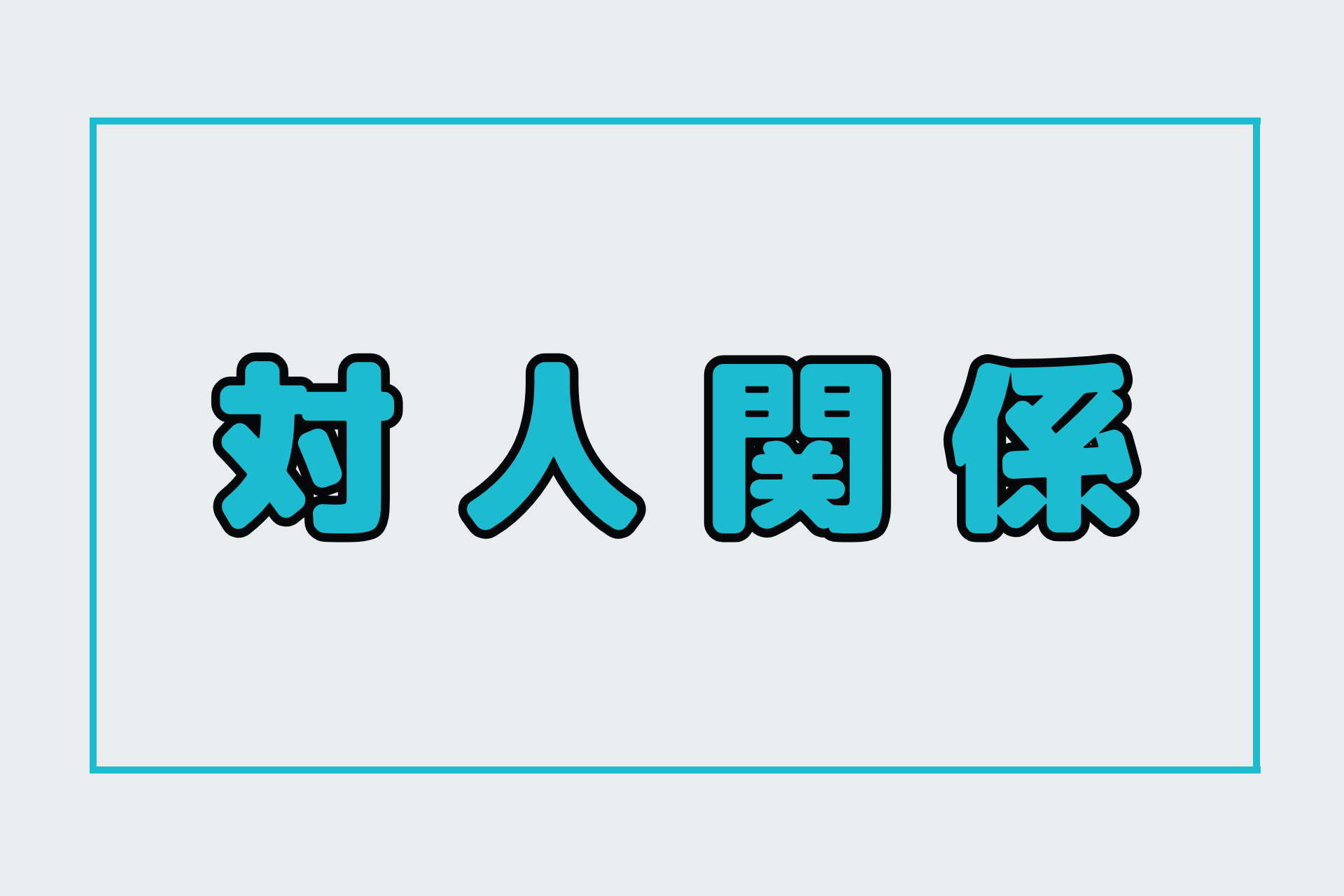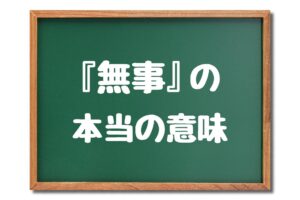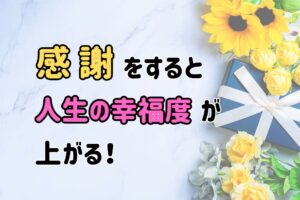人とのコミュニケーションに欠かせない【挨拶】。
元気に挨拶すると空気が和らぎ、相手の表情も自然とほころびますよね。
逆に、気持ちのこもっていない挨拶は、どこかぎこちない空気をつくり出します。
じつは、この【挨拶】という言葉は仏教の修行から生まれたもの。
仏教での【挨拶】は単なるマナーではなく、人と人が心を通わせる大切な手段なのです。
この記事では【挨拶】の本当の意味と、仏教における深い教えを分かりやすく解説しています。
日頃の声がけに対する意識が大きく変わりますので最後まで読んでみてください。
この記事を書いている私『ちょっき』は、お坊さん歴30年。お坊さんに関する裏話や、人間関係の悩みを解消する内容について発信しています。
挨拶の意味
毎日の生活の中で、何気なく交わされている挨拶。
挨拶には人と人とをつなぐ橋のような役割があります。
じつは、【挨拶】は仏教の言葉で、特に『禅』の修行から生まれたものです。
『挨』も『拶』も《近づく》という意味
まずは、【挨拶】という熟語を分解してみましょう。
- 挨:押し開いて近づく、心を開いて接する
- 拶:迫る、近寄る
このように、『挨』と『拶』は両方とも【相手に近づく】ことを意味します。
つまり、【挨拶】には『お互いに近づき合い、相手の様子を伺う』という意味があるのです。
また、挨拶というのは、基本的に《自分から心を開いて近づいていく》というスタンスです。
お互いに自分から心を開くことで、単なる儀礼的なものではなく、相手を思いやる重要なコミュニケーションとなります。
『挨拶』とは禅の修行の一環
挨拶という言葉が、仏教の言葉、特に禅の修行の場で使われていたことをご存じの方は少ないでしょう。
禅宗の道場では、師僧と弟子との間でよく問答が行われます。
これは禅宗の大きな特徴で、言葉のやり取りの中で【弟子の悟りの深さや、修行の進み具合】を確かめるために行われるのです。
まず、師僧が弟子に問いかけをします、これを『一挨(いちあい)』といいます。
そして、その問いかけに対して弟子が答えます、これを『一拶(いっさつ)』といいます。
このような一挨と一拶で問答することを、禅宗では『一挨一拶(いちあいいっさつ)』と呼び、これが省略されて現在の【挨拶】になったのです。
しかし、師僧は一挨一拶を通じて、弟子の答えの内容だけを確認していたわけではありません。
じつは、師僧は弟子の体調や精神状態なども一緒に見ます。
ですから、一挨一拶というのは、修行のための問答だけでなく、師僧と弟子がコミュニケーションをとるという重要な意味もあるわけです。
挨拶は『気づかい』から始まる
本来の挨拶は、形式的な決まり文句のやりとりではありません。
現代社会ではビジネスマナーとして「挨拶は大切」と言われますが、それがただの義務感やマナーであれば仏教的な意味合いは失われます。
挨拶とは本来「相手のことを気にかけ、自分から心を開いて近づくこと」なので、
- 今日は元気がないな
- 何か心配事があるのかな
- 声をかけてみよう
といった『気づかい』から始まる行為なのです。
つまり、元気に挨拶することは「あなたのことを気にかけていますよ」という意思表示でもあるのです。
試しに、明日から普段よりも少しだけ思いやりの気持ちを込めて挨拶をしてみてください。
きっと相手の挨拶も変わり、いつも以上の『心の通じ合い』が感じられることでしょう。
まとめ
人と人が心を通わせるためには、お互いに声をかけ合い、表情を見るなどの気配りが大切です。
それを簡単に始められるのが【挨拶】。
相手を気にかけ、自分から心を開いて歩み寄ることが仏教の【挨拶】です。
明日からぜひ、今までよりも少しだけ相手のことを思いながら挨拶をしてみてください。
そんな挨拶が、あなた自身に、そして相手にも良い影響を与えることでしょう。
※仏教由来の日本語は他にもたくさんあります。