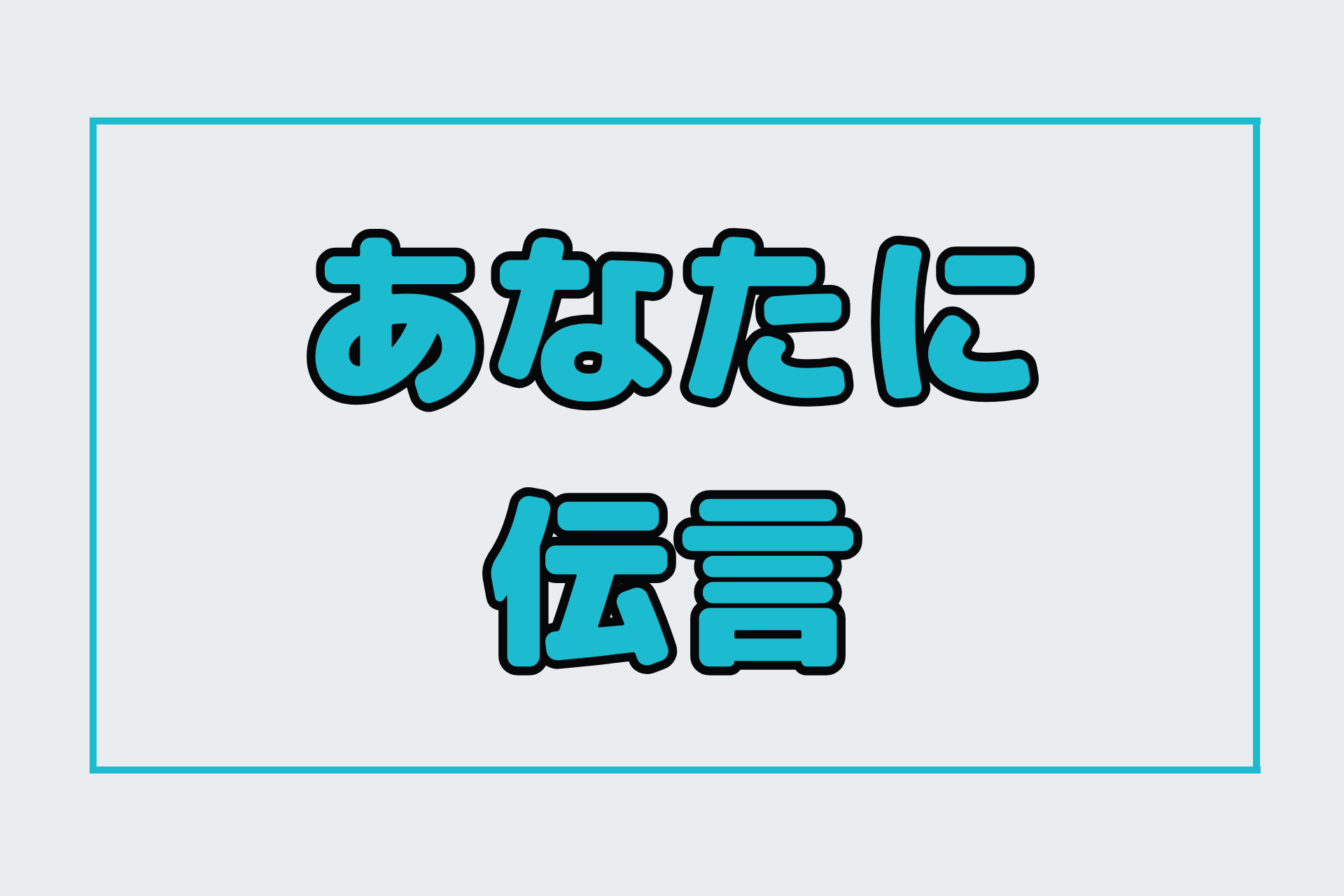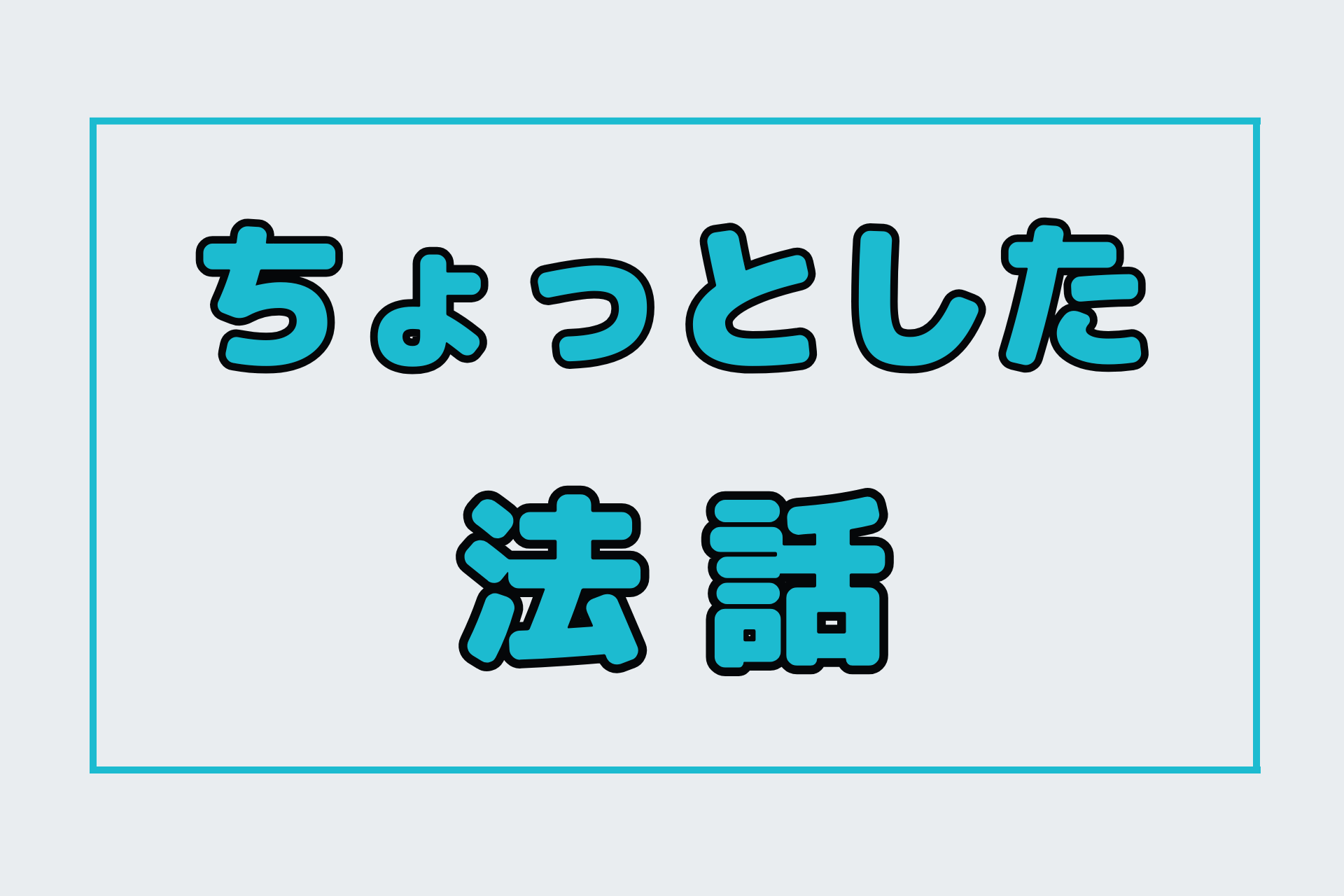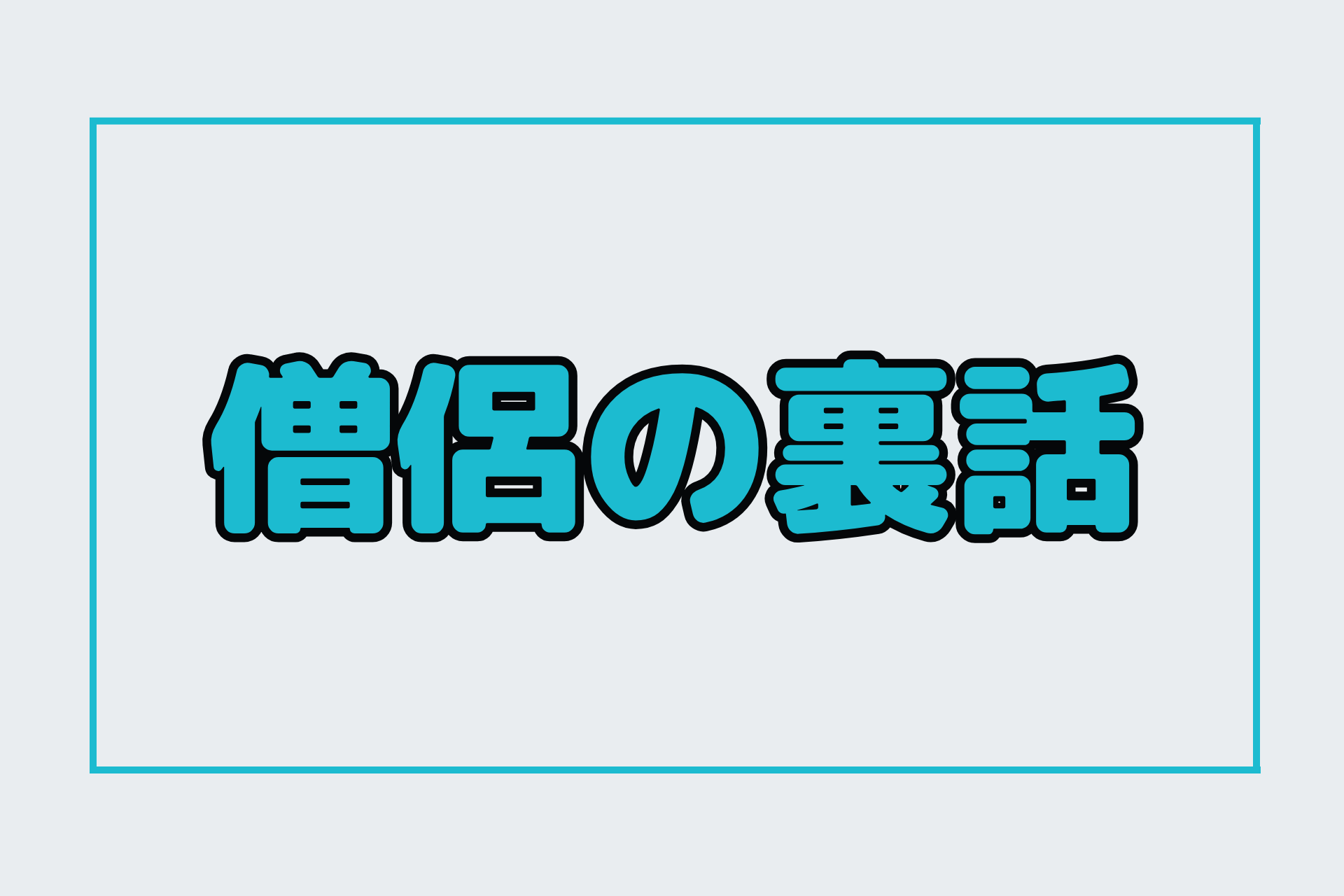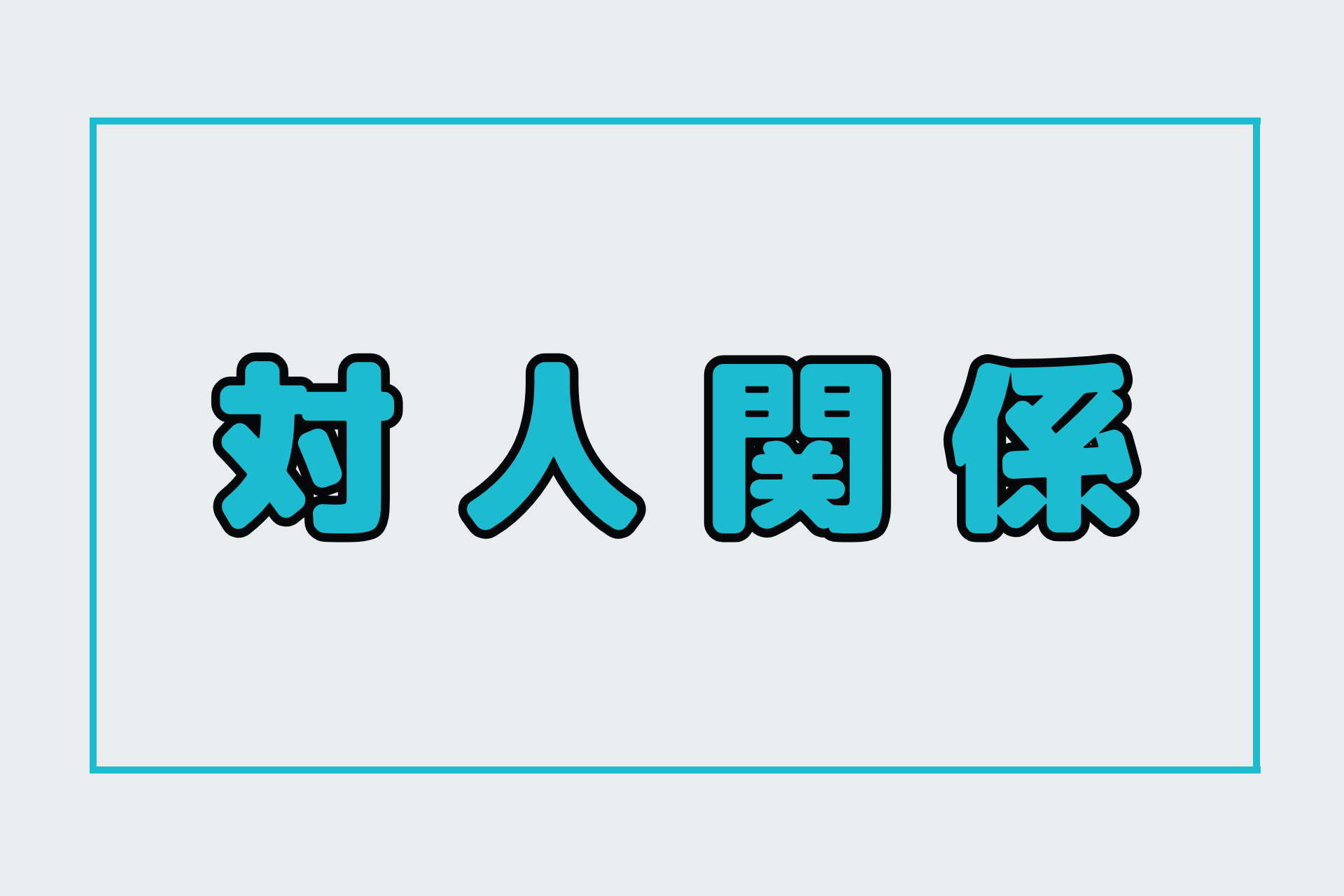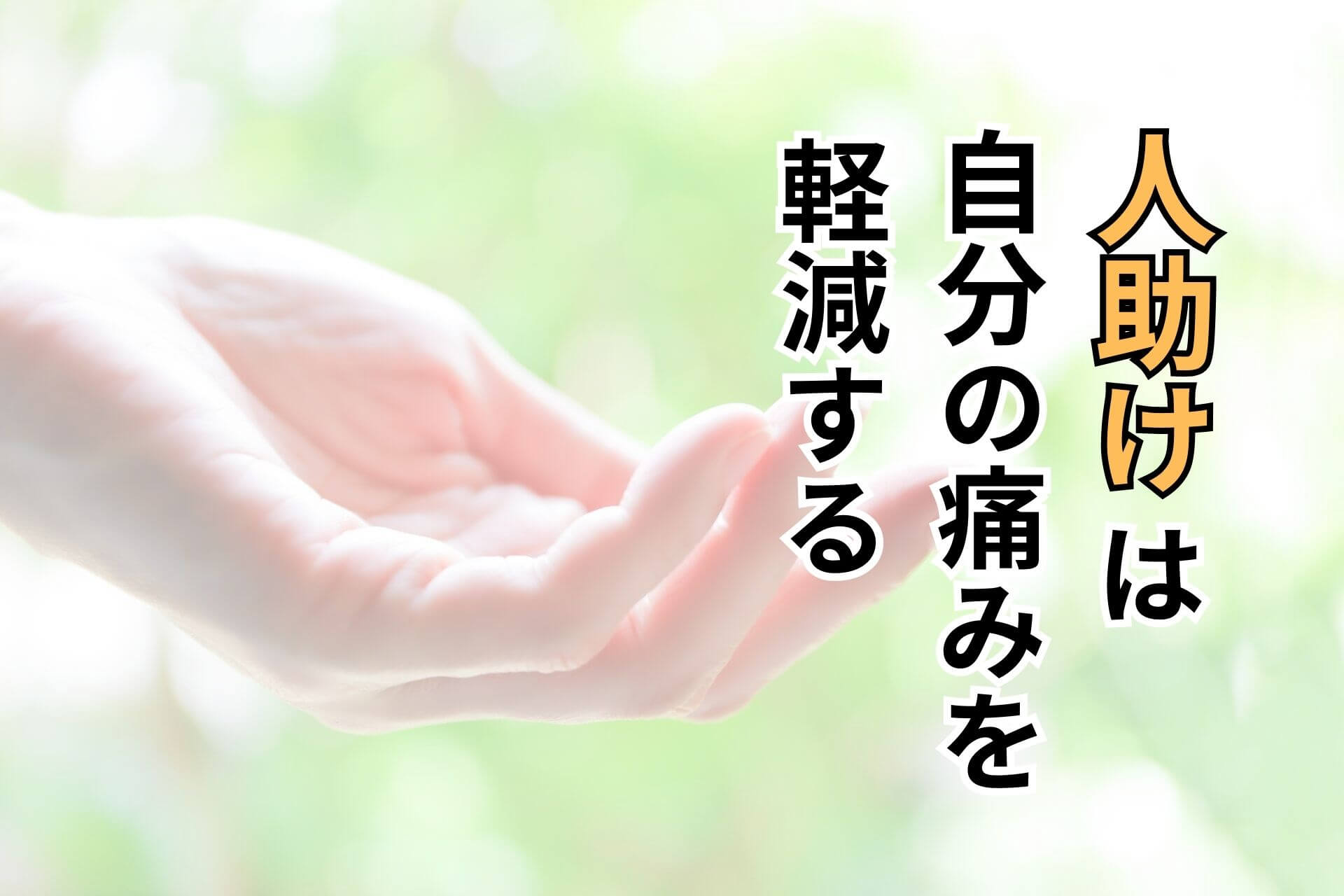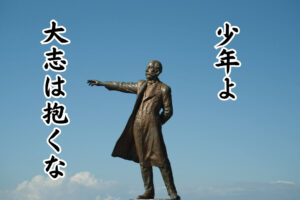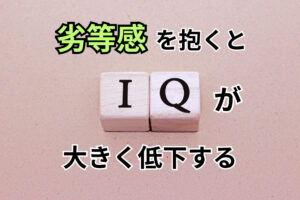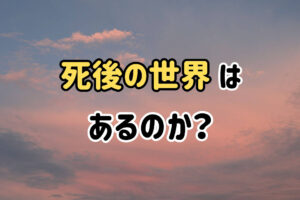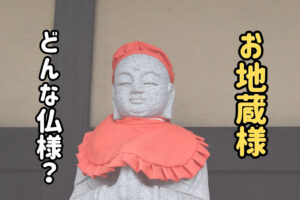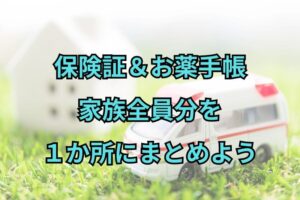あなたは日頃から『人助け』をしていますか?
例えば、電車で席を譲る、道に迷った人に道案内する、などいろいろありますよね。
もちろん、何をすれば人助けになるのか、という基準は人によって違います。
しかし、実際のところ、日常生活で人助けをする機会というのは意外と少ないでしょう。
じつは、人助けをすると私たちの《体の痛み》が軽減されるのです。
この記事では、人助けをすることの意外な効果について解説しています。
今までとは違う視点から【助け合うことの重要性】が分かりますので最後まで読んでみてください。
この記事を書いている私『ちょっき』は、お坊さん歴30年。お坊さんに関する裏話や、人間関係の悩みを解消する内容について発信しています。
体の痛みを和らげる『人助け』の効果
突然ですが、あなたは肩こりや腰痛、頭痛などの【慢性的な痛み】に悩まされていませんか?
もしも「はい。」と答えるなら、ぜひ『人助け』をしてみてください。
じつは、北京大学(中国)の研究によれば、人は見返りを求めず他人を助けると《体の痛み》に強くなるという結果が出ているのです。
北京大学の研究
中国の北京大学の研究チームは、他人を助けると体にどのような影響があるのかを調べました。
まず注目したのは【献血】。
献血をするときには注射針を刺しますので、このときの痛みの感じ方を調べたのです。
研究チームは献血をした人たちを【ボランティア経験がある人】と【ボランティア経験がない人】に分けて比較をしました。
その結果、日頃からボランティアをしている人の方が注射の痛みが小さいことが分かりました。
次に、より重い痛みを経験している人々を対象に調査をしました。
同じレベルの《がん患者》を集め、先ほどと同様に【ボランティア経験がある人】と【ボランティア経験がない人】に分けて比較をしたのです。
すると、ボランティア経験のある患者の方が痛みに対して強いという結果が出ました。
さらには、貧しい国の子どもたちに募金をした人と、しなかった人に対して軽い電気ショックを与える実験をしました。
すると、やはり募金をした人の方が痛みを感じにくいという結果が出たのです。
もちろん、痛みの感じ方は人によって異なります。
そのため、これらの研究は被験者たちの自己申告ではなく、脳波を計測した上で科学的なデータを取っていました。
つまり、『人助け』をすることで痛みの感じ方が変化することが科学的に証明されたわけです。
災害時に見られる『助ける力』
人助けによる痛み軽減の効果は災害時にも発揮されます。
日本は地震や台風の被害が多い国で、実際に数年おきに大きな自然災害が発生しておりニュースでは被災地の様子が放送されます。
そんな被災地の中で、自分自身もケガをしているにもかかわらず、必死に他の被災者を助けている人がいますよね。
そんな様子を見ていると、助けている人の素晴らしい人間性を感じます。
しかし、心理学的に見れば、他人を助けることで自分の痛みを軽減している側面もあるのです。
もちろん無意識ではありますが、他人を助けることによって同時に自分自身も助けているわけです。
ですから、自分が苦しいときこそ積極的に他人を助けてあげましょう。
なぜ痛みが軽減されるのか
なぜ人助けをすると痛みが軽減されるのでしょうか?
脳の働き
痛みが軽減されるのは『脳の働き』にポイントがあります。
人は他人を助けることによりポジティブな気持ちになり、脳からドーパミンという神経伝達物質が分泌されます。
ドーパミンは【やる気】を生み出す物質として有名ですが、じつは【痛みを和らげる作用】もあるのです。
例えば、マラソンランナーが長時間走っていても苦痛を感じにくくなる『ランナーズハイ』とう現象があります。
それと同じように、人助けをすれば『ヘルパーズハイ』という状態となるため、これにより痛みを感じにくくなるのです。
人間は助け合うようにできている
人間は1人だけで生きていくことはできません。
人間社会は常に《助け合い》で成り立っています。
自分が苦しいときでも他人を助け、その結果、自分自身もラクになり、さらにまた助け合いが広がっていきます。
これは単なる道徳ではなく、人間が本来持っている生存戦略なのでしょう。
お互いに助け合うことで人間社会が維持され、結果的に個人も守られる。
人助けによる体の痛みの軽減は、社会維持のメカニズムを裏づける科学的な現象なのです。
『人助け』の仏教的な視点
ここからは、『人助け』を仏教的な視点で考えてみます。
お釈迦様は【布施】つまり他者へ施すことをとても大事に考えました。
多くの人は【布施】と聞けば『お金や物を施すこと』を連想すると思いますが、仏教ではもっと広い意味があります。
布施というのは、
- 笑顔で接する
- 優しい言葉をかける
- 手助けをする
など、自分のできる範囲で誰かを助けること全部を指すのです。
そして、布施を続けることで、巡り巡ってやがて自分のところへ恩恵として返ってくると説いています。
つまり、『人助け』という布施をすることにより、自分の心と体をラクにするという恩恵として返ってくるのです。
これは、まさに現代科学が証明した《人助けは体の痛みを軽減する》という事実と一致しています。
2,500年前からこの真理に気づいていたお釈迦様、改めてその偉大さを思い知らされます。
『人助け』をするときのコツ
『人助け』をすると自分もラクになりますが、何でもかんでも助ければいいというものではなく、ちょっとしたコツがあるのです。
『人助け』をするときには【無理のない範囲で、なおかつ短時間で済むこと】を心がけてください。
もっと具体的に言えば、【自分の得意分野で、なおかつ5分以内に終わること】で助けてあげてください。
そうすれば、時間や手間があまりかからないため労力が少なく、また、お互いにとって心理的な負担も少なくて済みます。
例えば、
- 電車やバスで席を譲る
- ドアを押さえて後ろの人が通りやすいようにする
- 職場で困っている同僚の手伝いをする(5分以内)
- 道に迷っている人に声をかける
など、これらも立派な『人助け』になっています。
しかし、助けられた人にとっては大きな意味があり、助けた自分にとっても《ヘルパーズハイ》となって心身ともに安らぐ効果があるのです。
まとめ
『人助け』は自分の体の痛みを軽減してくれます。
他人を助けることにより脳内からドーパミンが分泌され、自分自身の痛みを感じにくくなるのです。
仏教でも【布施】として『人助け』をすると、巡り巡ってやがて自分の元へ恩恵として返ると説いています。
ですから、『人助け』は結果的に『自分助け』にもなるのです。
もしもあなたが慢性的な痛みでお困りなら、薬だけでなく《ちょっとした人助け》をしてみてください。
その小さな行動が、あなたの心と体を癒してくれるかもしれません。
※こちらの記事も読まれています。