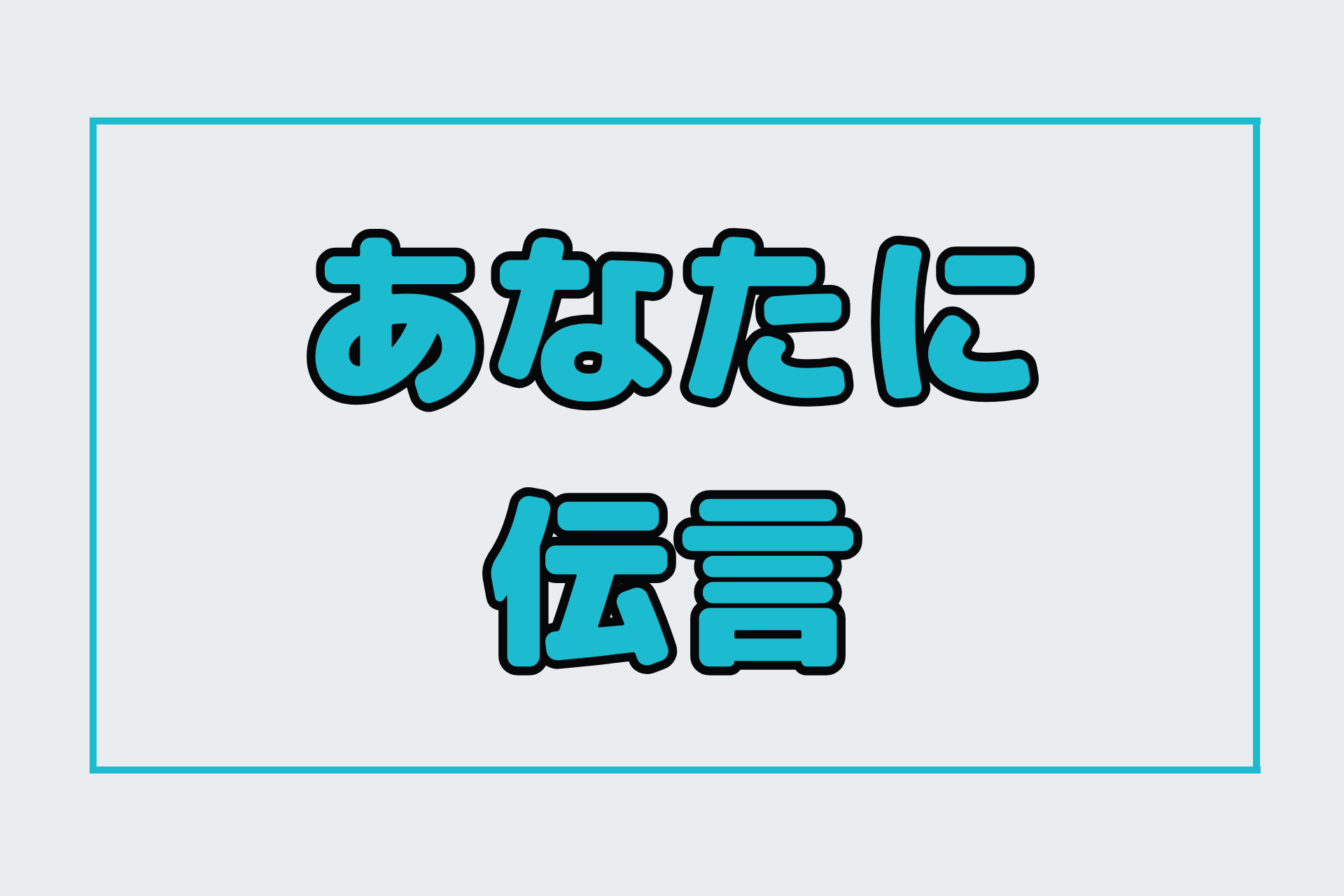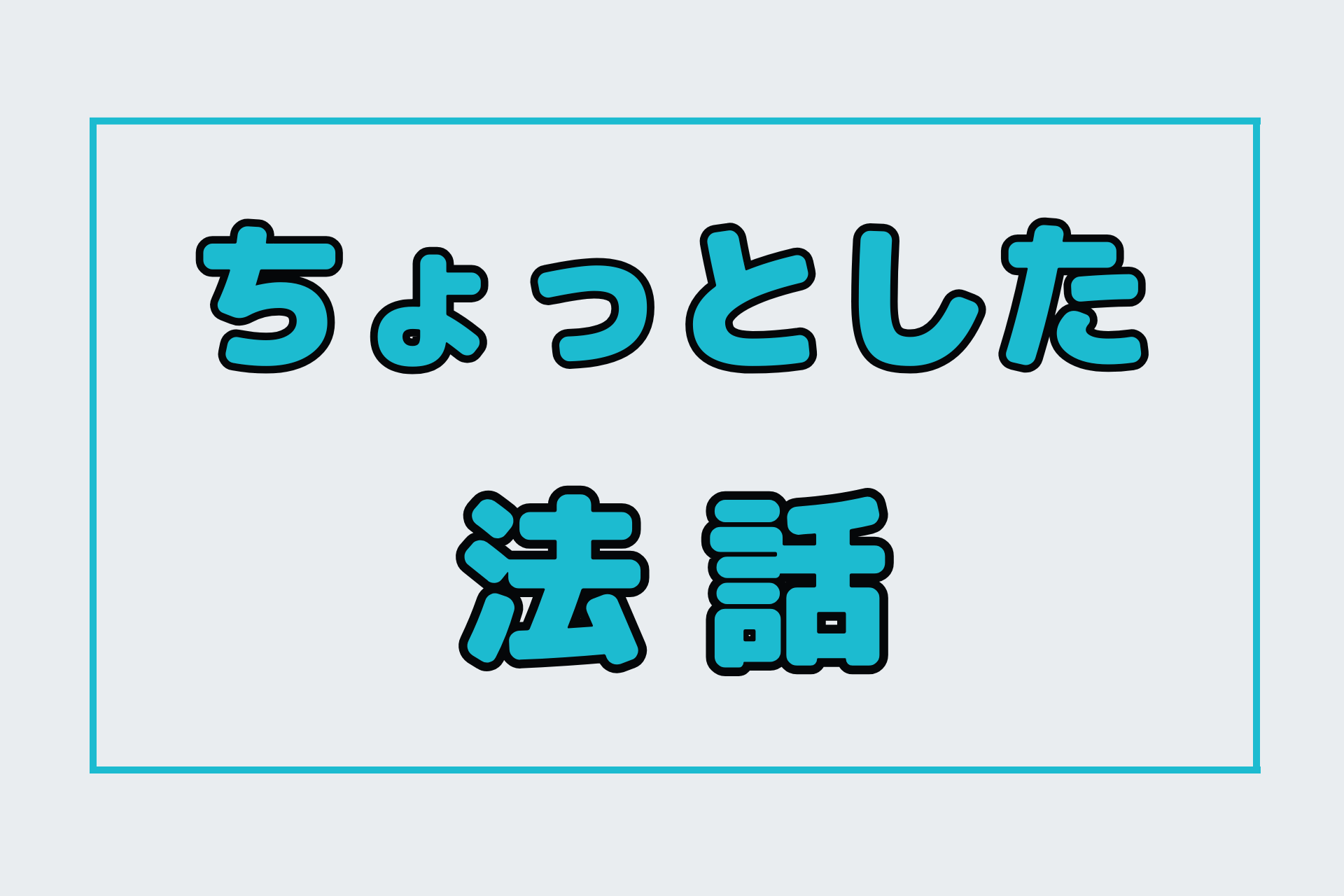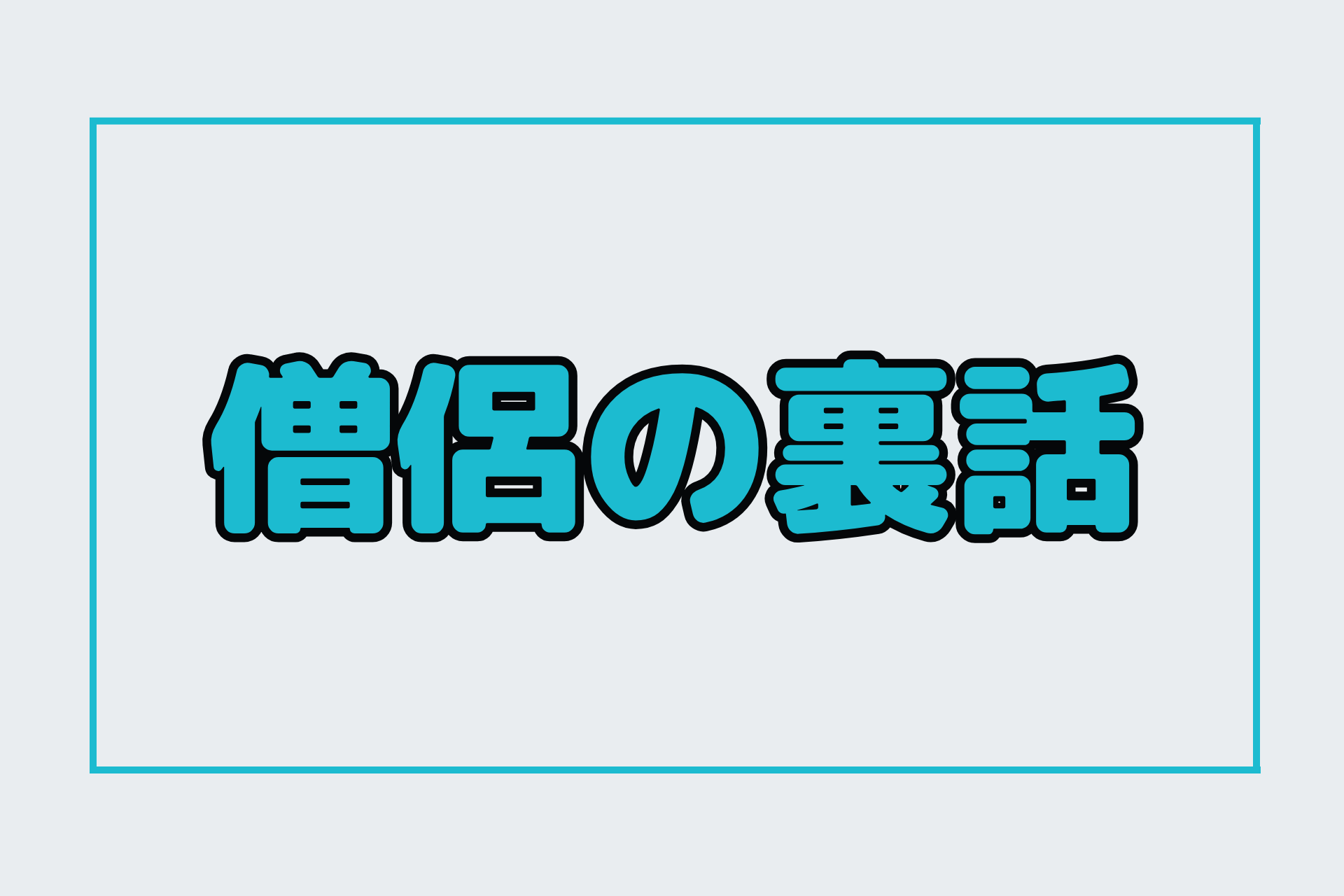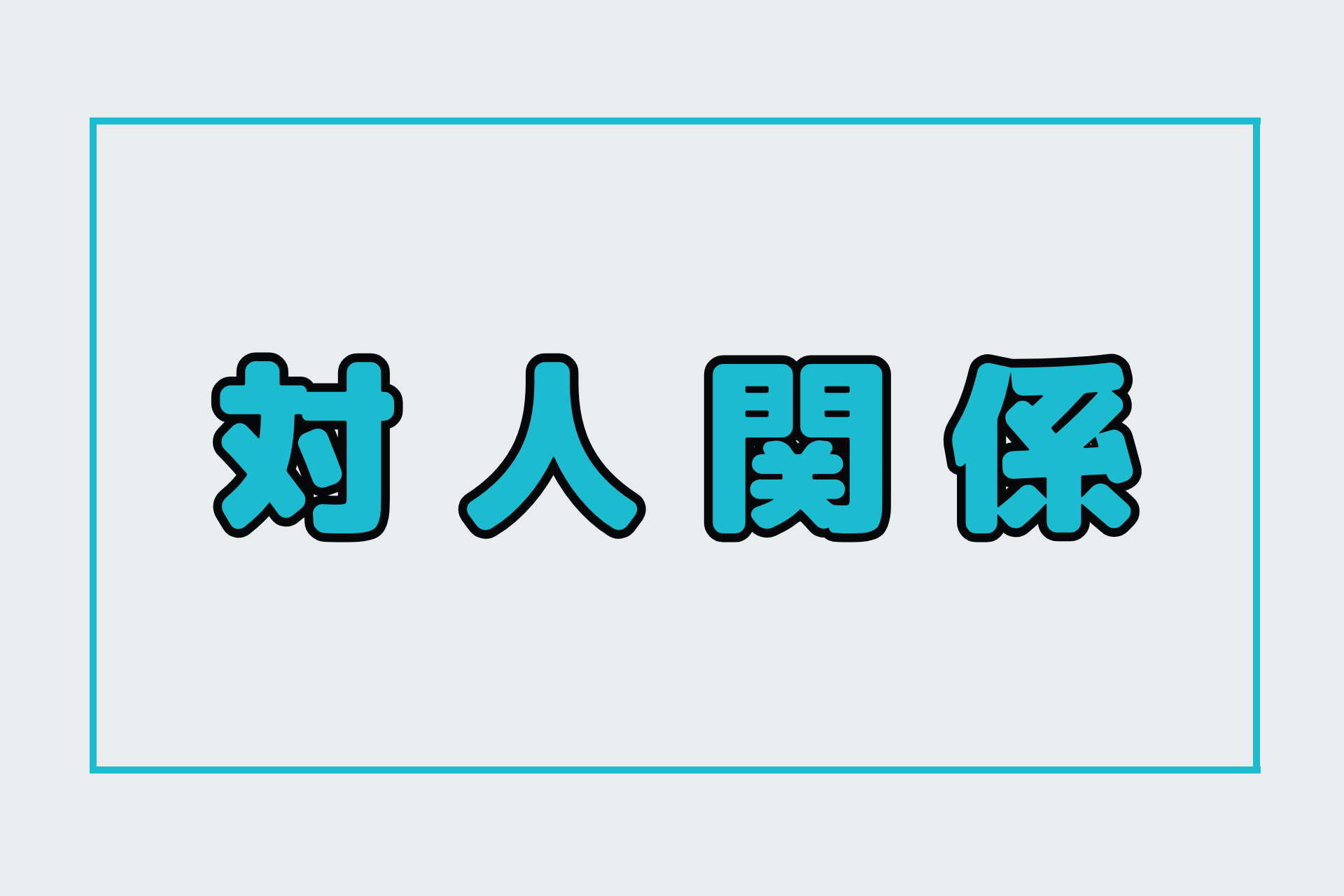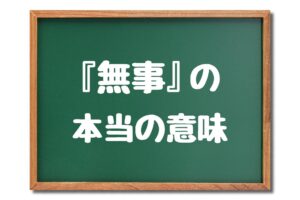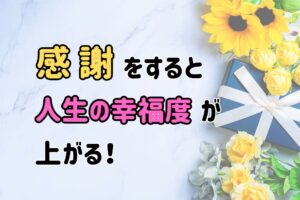あなたは「宗教」という言葉を聞いてどんな印象を抱きますか?
『怪しい』とか『うさんくさい』と思うでしょうか?
「宗教」と聞くだけで何となく距離を置きたくなるのは現代社会ではよくあることです。
しかし、僧侶の立場で申し上げると、宗教はあった方がいいと思います。
宗教があることで、心を豊かにし、よりよい人生を歩むためのヒントに気づくことができます。
この記事では『宗教の必要性』について、西洋の諺と、簡単な昔話を交えながら解説しています。
この記事を書いている私『ちょっき』は、お坊さん歴30年。お坊さんに関する裏話や、人間関係の悩みを解消する内容について発信しています。
西洋の諺『宗教なき教育は賢い悪魔をつくる』
ヨーロッパで古くから伝わる諺に、『宗教なき教育は賢い悪魔をつくる』というものがあります。
この諺は、宗教によって心を育てないと、知識ばかりの悪魔が出来上がってしまうことを教えています。
教育とは、ただ単に知識を詰め込むことではありません。
教育とは、『人としてより良く生きる』ために【心】を育てることでもあります。
いろんな知識や技術を身につけても、それをどう正しく使うのかを判断するのは【心】です。
ですから、ちゃんと心が育っていなければ、周囲を思いやることも、自分を律することもできず、知識ばかりの『賢い悪魔』が出来上がります。
賢い悪魔になってしまうと、私利私欲のために知識を使い、周囲の人々を平気で傷つけてしまいます。
そのため、賢い悪魔は、家庭や社会を《破壊》することはできても、皆が幸せになるものを《作り出す》ことができないのです。
そんな賢い悪魔とならないように、そして心豊かな人生を歩むためにも、家庭には宗教があった方がよいというのがこの諺の教えです。
現代の私たちは便利な物に囲まれ、物質的な幸福は十分にあります。
しかし、物質的な幸福だけを追い求めると、心の幸福が軽視され、結果的に賢い悪魔が生まれてしまいます。
物で栄えて心が滅ぶなんていうことがないようにしなくてはいけません。
宗教というのは、私利私欲のために使うと害悪になりますが、正しく使えば温かな家庭を築き、また心豊かな人生を送るための教科書となるのです。
宗教が家庭にあるということ
家庭には宗教があった方がいいです。
では、「宗教がある家庭」とは、どのような家庭なのでしょうか。
ここで1つ昔話を紹介します。
昔、ある家に目の不自由なお婆さんがいました。
その家には息子さんとお嫁さん、そして孫にあたる小さな子供が一緒に暮らしていました。
しかし、お嫁さんは、日頃からお婆さんに冷たく、食事のときにもひどい扱いをしていたのです。
目の不自由なお婆さんは、どうしてもご飯をこぼしてしまいます。
お嫁さんは「ご飯をこぼして畳が汚れるから」と言って、お婆さん用の食べ物を《薄汚い木箱》にすべて放り込んで食べさせていました。人としての尊厳を無視した行為です。
そんなある日、子供が庭で木の板を集めて何かを作っていました。
その様子を見たお嫁さんは「あら、何を作っているの?」と訊ねます。
すると、子供は得意げに、
「お母さんのために木箱を作っているんだよ!だって、お母さんも年をとって、おばあちゃんになったら必要でしょ?今のおばあちゃんみたいに、ご飯を入れる箱を用意しておかなくちゃね。」
と答えたのです。
それを聞いたお嫁さんは、はっと胸を突かれました。
「あぁ、私はなんていう姿を子供に見せていたのだろう。」と深く反省し、それからはすっかり心を改めてお婆さんを大事にしました。
この話が伝えているのは、大人の振る舞いが子供の心をつくる、ということです。
子供の頃は、見るもの聞くもの感じるものすべてを吸収して成長してゆきます。
ですから、家庭の中に思いやりがあるか、感謝の心があるか、といった家庭環境が子供の心の成長に大きく影響します。
そして、家庭において子供の心を作り出す大事な要素として宗教があるのです。
宗教とは何か
この記事のメインテーマである【宗教】。
ここで、宗教の『宗』という字に注目してみましょう。
『宗』という字は「むね」とも読みますよね。
「むね」と読む漢字は、他にも胸、棟、旨などがありますが、これらの漢字はどれも「中心」または「大もと」といった【重要なもの】を意味します。
そして、『宗』という字にも「中心」や「大もと」という意味があります。
つまり、宗教というのは、私たちの人生の中心となる【重要な教え】という意味があるのです。
そして、先述したように、宗教は家庭においても重要です。
仏壇に手を合わせることで、ご先祖様達がいたおかげで自分が今ここに存在していることを実感できます。
食事のときには「いただきます」と手を合わせ、自分が《頂いている命》によって生かされていることを知ることができます。
これらは宗教が教えていることであり、そのような教えがある家庭とそうでない家庭では、子供の心を育てる環境が全く違ったものになるのです。
心の豊かさを育むもの
今の時代は、物質的にとても恵まれています。
便利な家電やインターネット、そして豊富な食べ物があり、生活するには困らない時代になりました。
しかし、一方で【心】が満たされない人が増えています。
人とのつながりが薄れ、自己中心的な考えが擁護され、家庭や社会での『思いやり』や『優しさ』が失われつつあるような気がします。
物質的に豊かになったところで、心が貧しくなってしまったら、何の意味があるでしょう?
物で栄えて、心で滅ぶ。
そんな社会にしないためにも、宗教を用いた心の教育が必要なのではないでしょうか。
まとめ
心豊かでより良い人生を歩むには、宗教はあった方がいいです。
知識や技術を習得していくことも大事ですが、同時に【心】を育てなくては『賢い悪魔』が生まれてしまします。
心を育てるためには、家庭でも宗教を取り入れることが大事です。
宗教は人生の中心となる『心の教科書』であり、家庭に思いやりや感謝の心を育むチカラがあります。
どんなに物がたくさんあっても、心が貧しければ幸せにはなれません。
だからこそ、家庭には宗教が必要なのです。
※こちらの記事も読んでみてください。