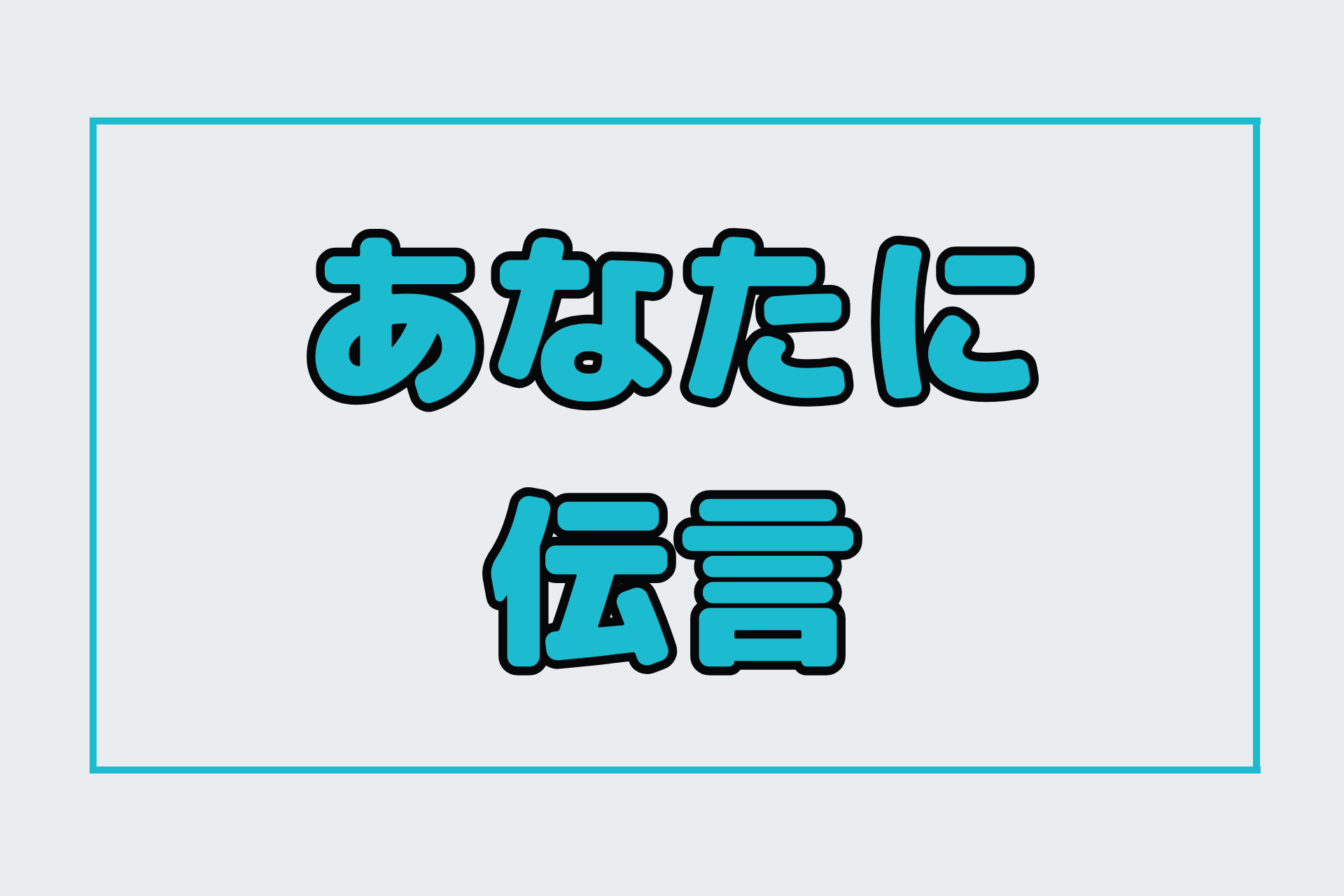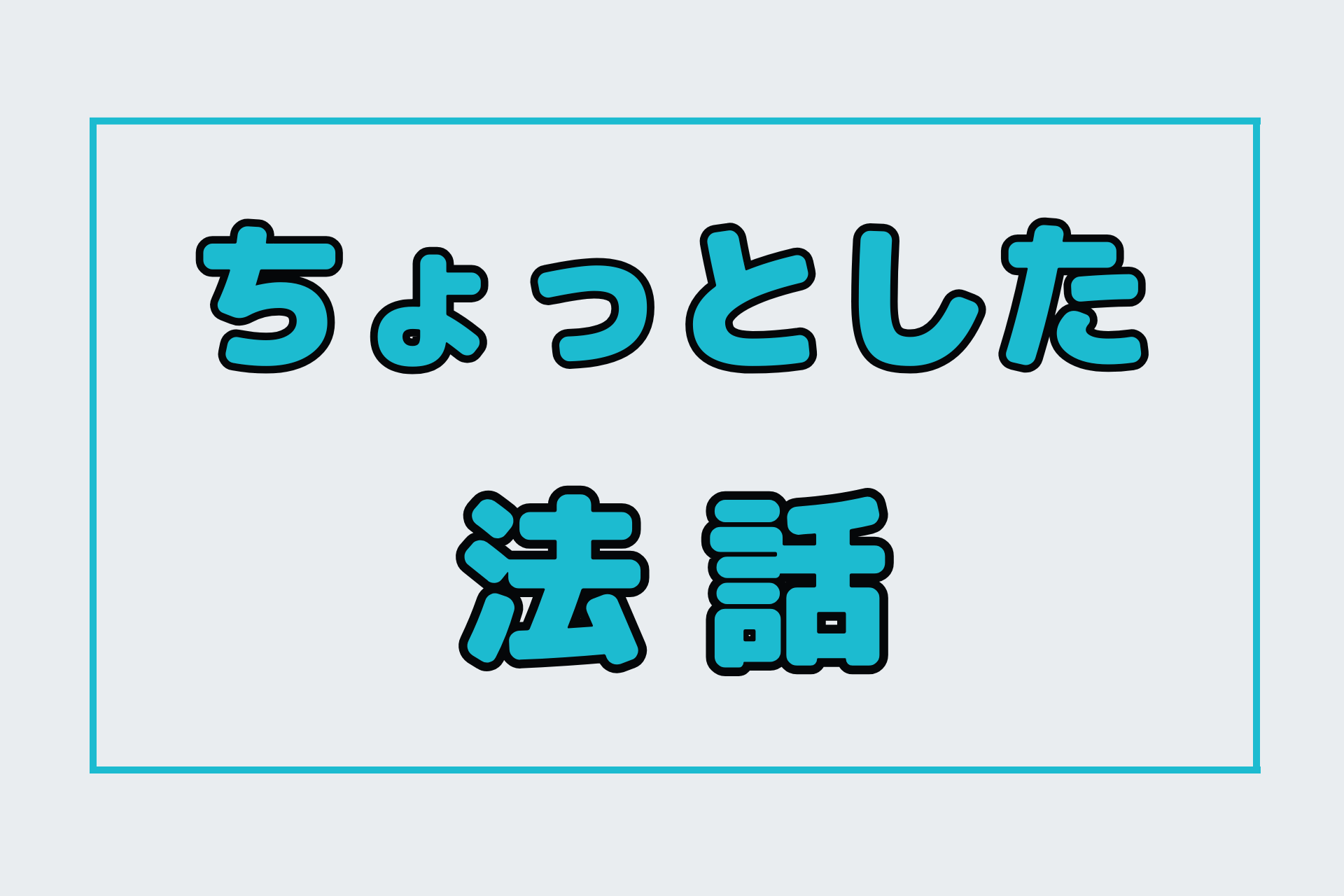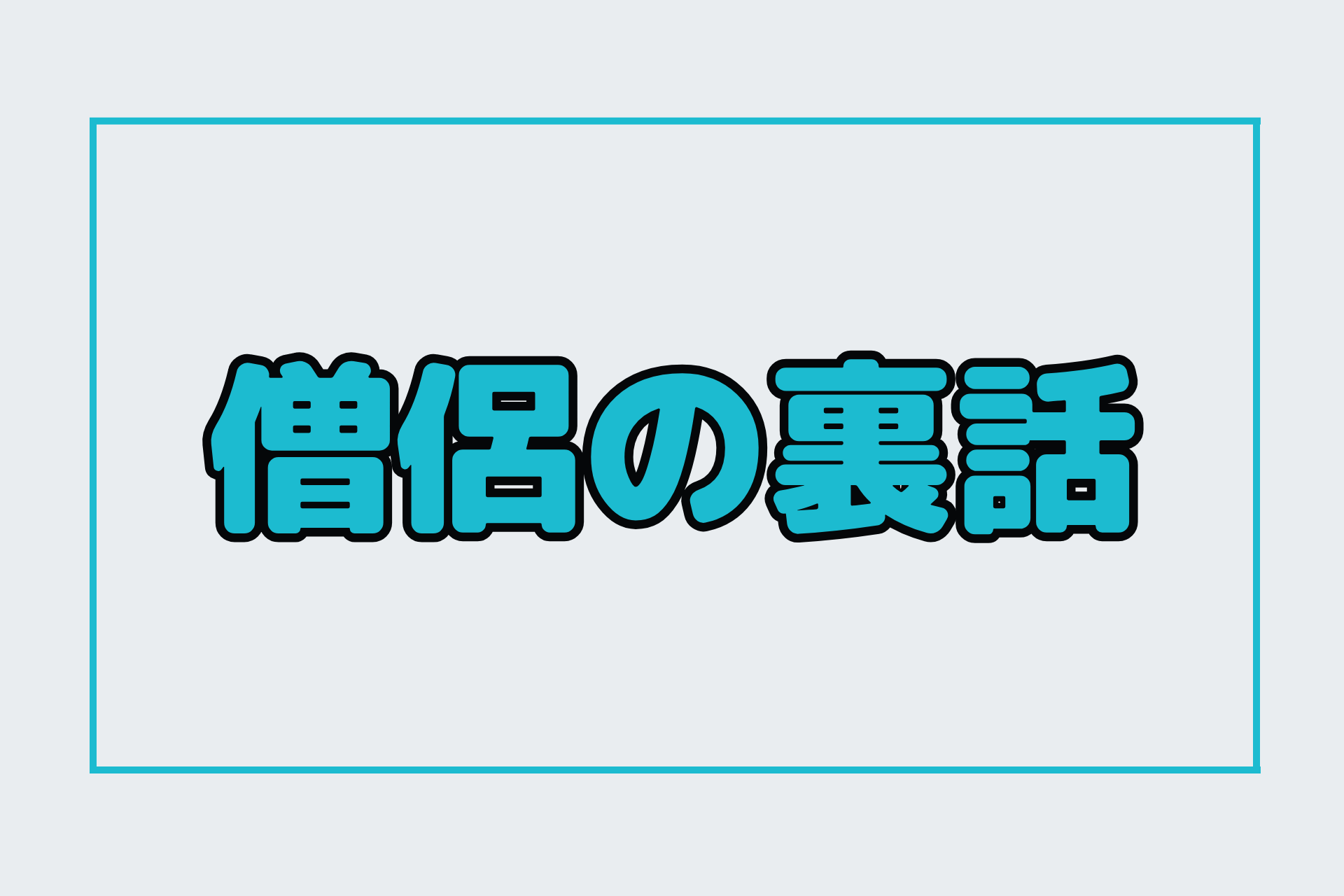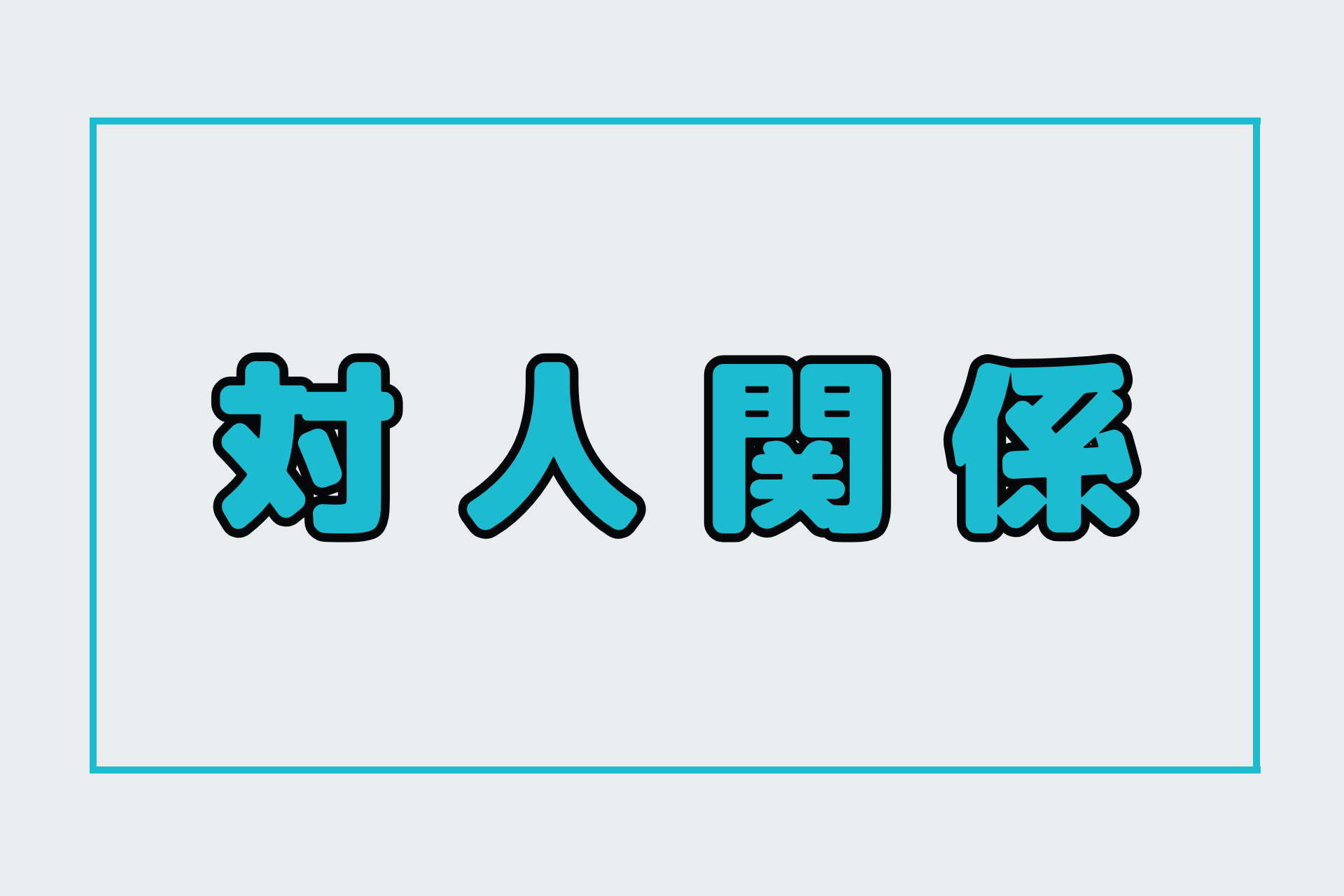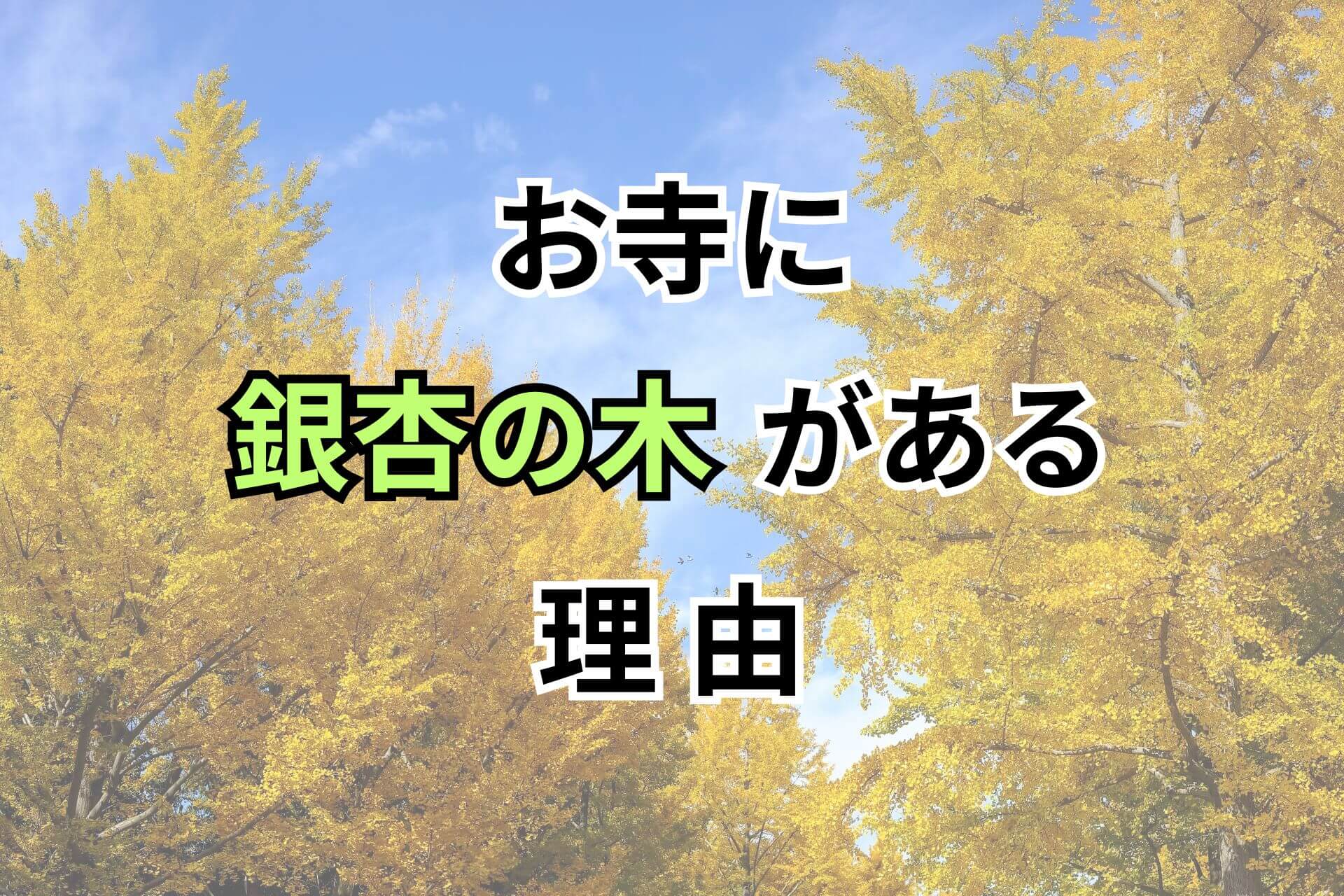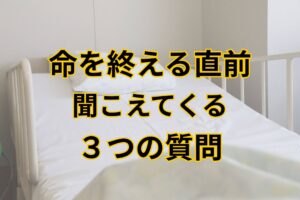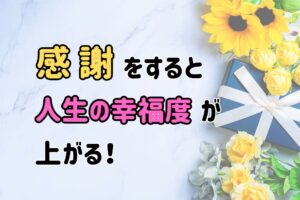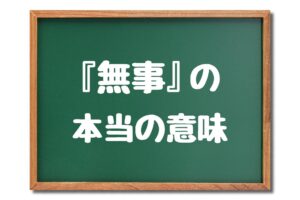お寺にはいろんな木があります。
お寺によっては、地域のシンボルとなるような大木があったり、国や市区町村の保存樹木になっている木もあります。
木にはたくさんの種類がありますが、じつは、お寺にあるのは『銀杏(いちょう)の木』が多いです。
そして、お寺に銀杏の木が多いのにはそれなりに理由があります。
本記事では【銀杏の木がお寺に植えられている理由】について紹介しています。
銀杏の木に対する見方が少し変わりますので最後まで読んでみてください。
この記事を書いている私『ちょっき』は、お坊さん歴30年。お坊さんに関する裏話や、人間関係の悩みを解消する内容について発信しています。
お寺に【銀杏の木】がある理由
私がいる寺には大きな『銀杏』の木があります。
毎年、秋になると銀杏の木にたくさんの実がなり、それが落ちてくるわけですが、まぁその臭いがスゴイんですよね。
でも、銀杏の実の種は栄養価が高くて食べると美味しいので、落ちた銀杏の実を拾いに来る方もおられます。
とはいえ、誤って踏んでしまうと靴の裏に強烈なニオイが付着するので、あなたも銀杏の下を通るの際には足元に注意してください。
そんな銀杏の木ですが、じつはお寺に植えられることが多いんです。
銀杏の木は燃えにくい
よく「銀杏の木は火に強い」と言われます。
銀杏の葉というのは、他の植物の葉よりも水分が多いので燃えにくいのです。
また、葉だけではなく幹や枝にも水分が多いので、銀杏の木全体が火に強いんですよね。
そのため、【大事なものが燃えないように】また【火災が起こりませんように】という願いを込めて、大事な建物などの周りには銀杏の木を植えます。
そして、お寺も信者さんや地域の人のとって大事なものなので、万が一の火災から守るため、そもそも火災が起こらないようにと願って、多くのお寺では銀杏の木があるのです。
銀杏の葉の色素が抜ける
銀杏の葉は、時期が来れば緑色から黄色に変わっていきますよね。
あれは、葉の中にある葉緑体という緑色の成分があるのですが、光合成をしなくなることで葉緑体が抜けていき、最終的には銀杏の葉の元々の色である黄色が残るのです。
言ってみれば、銀杏の葉が『本来の姿に戻る』ということであり、ここが銀杏とお寺が関連しているところです。
仏教では、私たちはみんな【仏の要素】を持っていると考えています。
しかし、私たちには様々な欲望があり、それらが仏の要素を覆ってしまい、いつまでも仏として開花できません。
仏となって悟りを得るためには、欲望を一つずつ取り除き、最後に《仏の要素だけが残った状態》にしなくてはいけません。
ですから、銀杏の葉が本来の姿に戻るように、私たちも自分の本来の姿である仏に戻りましょう、という意味を込めてお寺に銀杏の木を植えることが多いんです。
銀杏は『不変』の象徴
銀杏の木は『不変』を象徴する木とされています。
なぜなら、銀杏は約1億5千万年前から地球上にあるといわれる植物だからです。
そのため、銀杏は《生きた化石》とも呼ばれており、その姿は【仏教が説く不変の真理】を象徴しているのです。
また、銀杏の木は寿命が長いこともあり、それが【お釈迦様の教えがずっと私たちの中に生き続けている】ということも象徴しています。
仏教的な教えが理由になっている
お寺に銀杏の木が多いのは、仏教的な教えに基づいた理由もあります。
諸行無常
銀杏の木は、仏教の有名な教えである【諸行無常】にも関係があります。
諸行無常というのは、簡単に言うと『あらゆるものは常に変化し続ける』という意味です。
銀杏の木もまた常に変化しながら生き続けています。
先ほど、銀杏の木は『不変』を象徴すると言いましたが、銀杏の木そのものは常に変化しています。
いくら不変を象徴するとはいえ、約1億5千万年前からそのままの状態で存在している銀杏の木はありません。
枝が伸びて、葉や実をつけ、やがて葉や実が落ち、そして再び枝が伸びる。
このように、ずっと銀杏の木として存在していますが、銀杏の木そのものは常に変化しており、それが諸行無常の教えを象徴しているのです。
輪廻転生
銀杏の木は、仏教の【輪廻転生】という考え方にも関係があります。
銀杏はいわゆる『落葉樹』なので、秋になると黄色くなった葉が落ちて、木の周辺を黄色い絨毯に変えます。
そして、落ちた葉は地中で栄養分として銀杏の木に吸収され、春になると新芽として再び命を授かるのです。
これが、「すべての命は生死を繰り返し、新たな命として生まれ変わる。」という【輪廻転生】の世界観に通じるわけです。
無量光
銀杏の木は、葉が黄色になることから【智慧の光】とも関連づけられています。
智慧の光は、正しい道を照らし出し、私たちの欲望や執着といった煩悩を取り除いてくれます。
また、阿弥陀様から放たれる智慧の光は、決して絶えることのない慈愛の光であるため《無量光》と呼ばれています。
お寺に銀杏の木があることで、いつでも阿弥陀様が私たちを見守り導いてくださっていることを想起させてくれるのです。
中道
銀杏の木は、仏教の【中道】という教えにも関連しています。
中道というのは『物事は両極端に考えず、その中間を目指して考えるのがよい』という教えです。
例えば、健康的な体型を維持するためには、食べ過ぎてはいけませんし、だからといって極端なダイエットをするのも逆効果となります。
適切な食材を適切な量だけ食べるという、どちらにも偏らない食事をすることが健康的な体型を維持するコツです。
このように、極端な考え方では本質を見失うので、そうならないために中間的な考え方をするのが【中道】です。
そして、銀杏の葉は【中道】の教えを象徴しています。
銀杏の葉の《形》は『二股』に分かれていますよね。
これが、つい物事を両極端に考えてしまう私たちを表し、また、両極端な考えの元となる本質の部分を見直しなさいという教えも表しているのです。
阿字のふるさと
黄色くなった銀杏の葉は、やがて枝から落ちて母なる大地へ帰ります。
じつは、ここにも仏教的な教えがあります。
例えば、真言宗の教えによると、私たちは人として生まれる前には大日如来という仏様の元にいると考えています。
大日如来という仏様は『阿』という文字で表現されるため、大日如来のいる世界を【阿字のふるさと】といったりします。
そして、私たちは【阿字のふるさと】から一度離れてこの世に生まれ、様々な経験を通じて成長し、そして再び【阿字のふるさと】へ帰るのです。
銀杏がたくさん実をつけてから葉が落ちるように、私たちも充実した日々をすごし、悔いのない人生を送り、胸を張って【阿字のふるさと】に帰りましょう。
まとめ
多くのお寺にある銀杏の木。
銀杏の木は、お寺を火災から守るため、そして火災が起こらないように祈って植えられています。
また、防火上の理由だけではなく、仏教的な教えを象徴するものでもあります。
今度どこかのお寺を訪れたときに銀杏の木があったら、近くまで行って銀杏の木を見上げてみてください。
きっと、銀杏の木が仏の教えを静かに伝えてくれるでしょう。
※こちらの記事も読んでみてください。