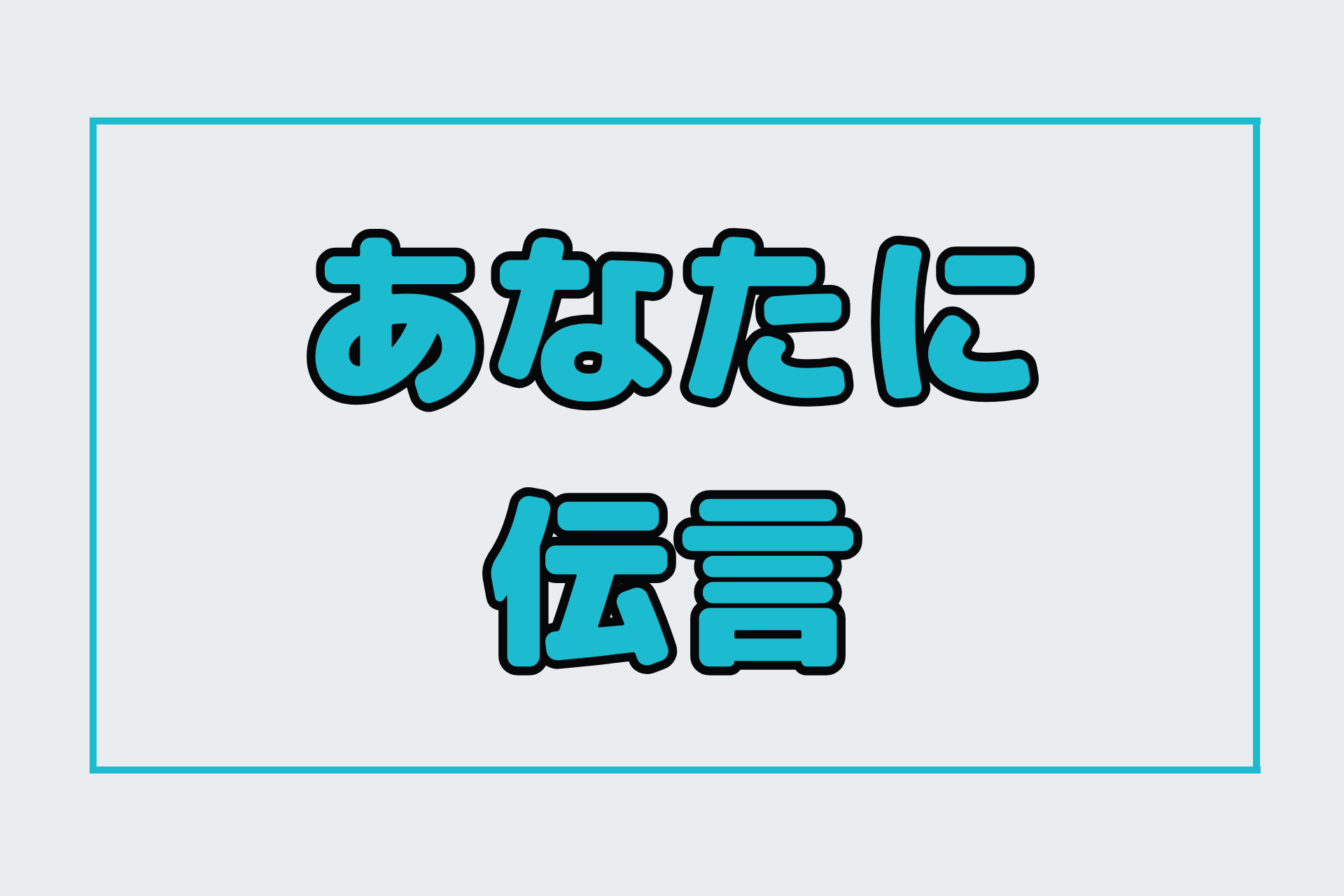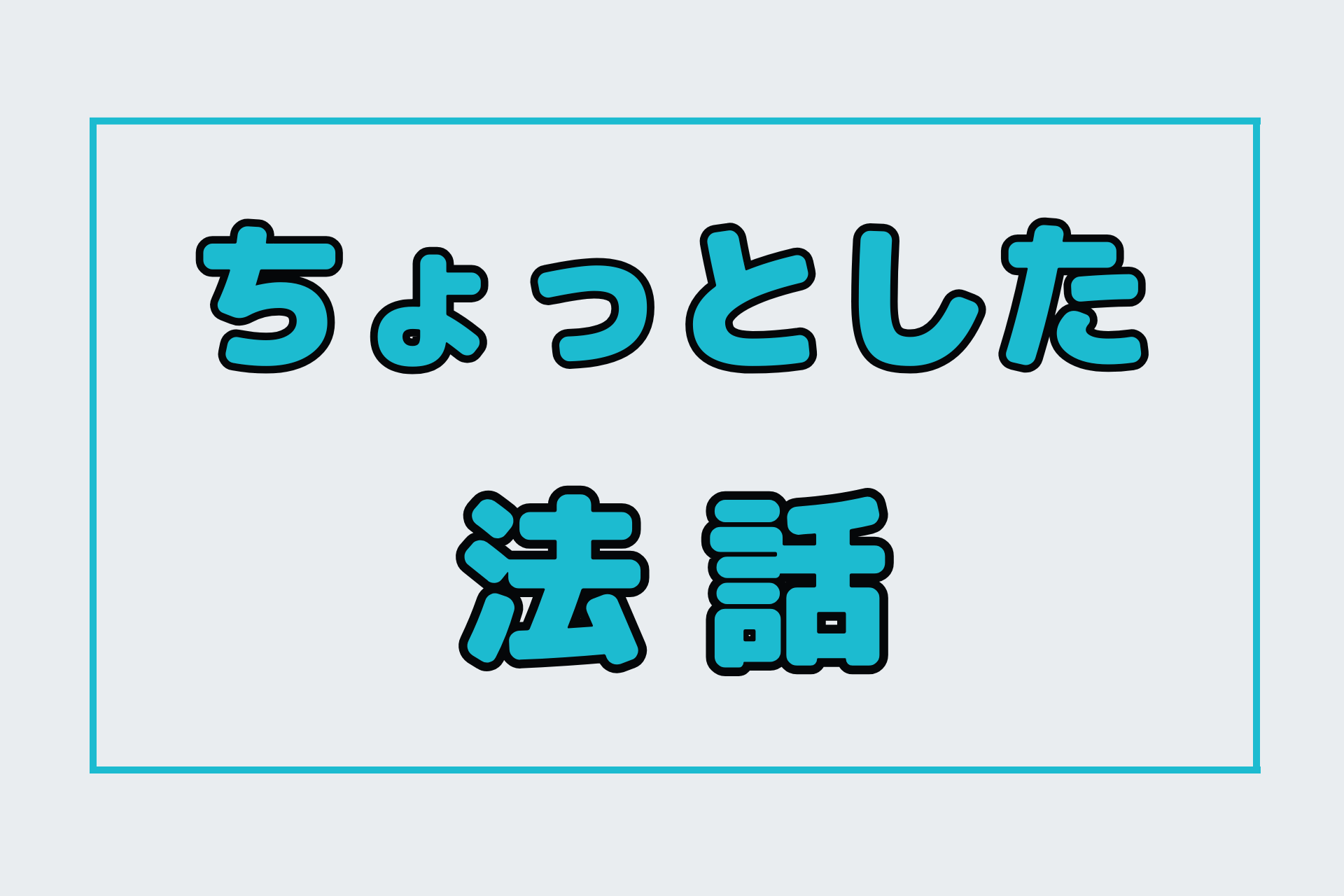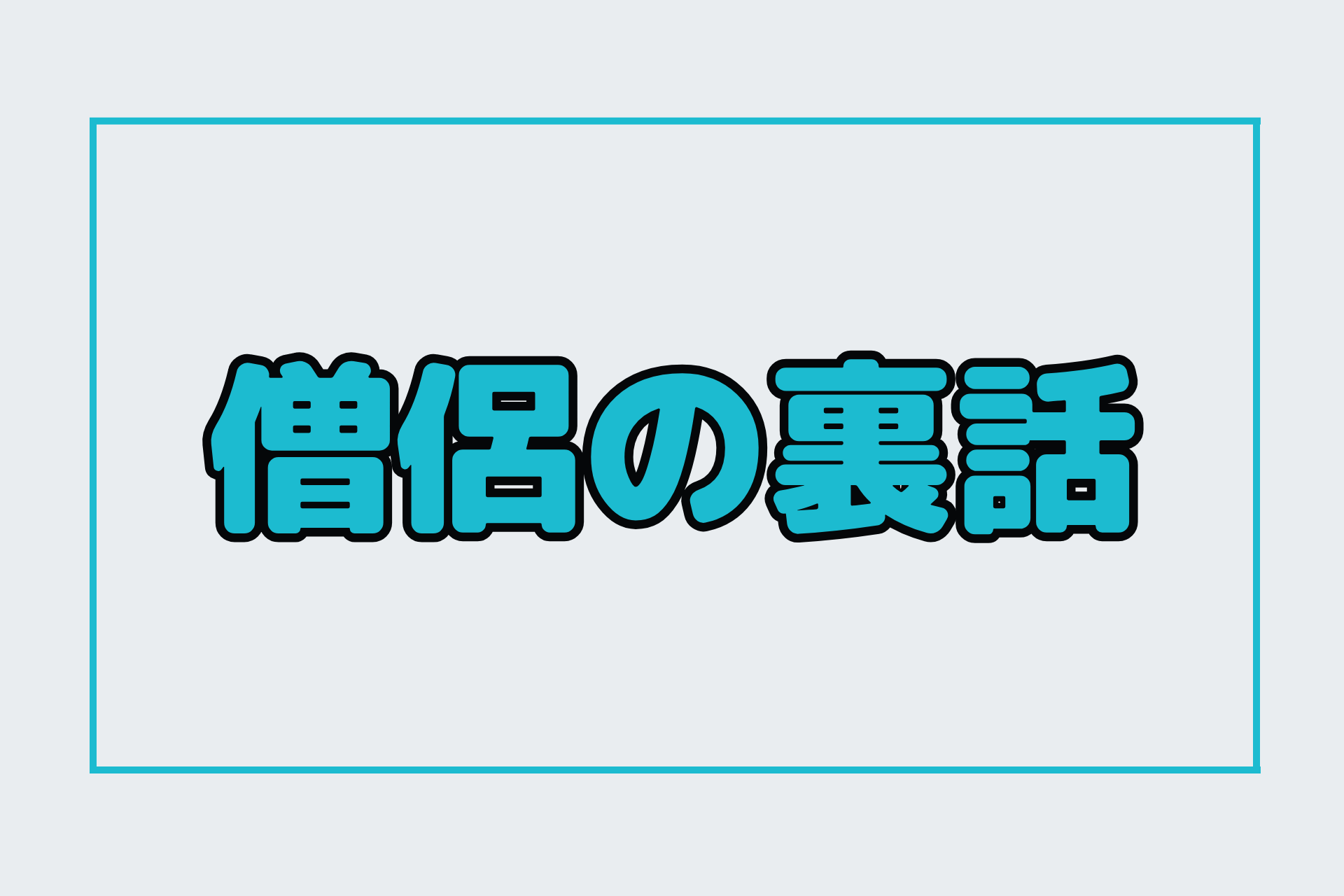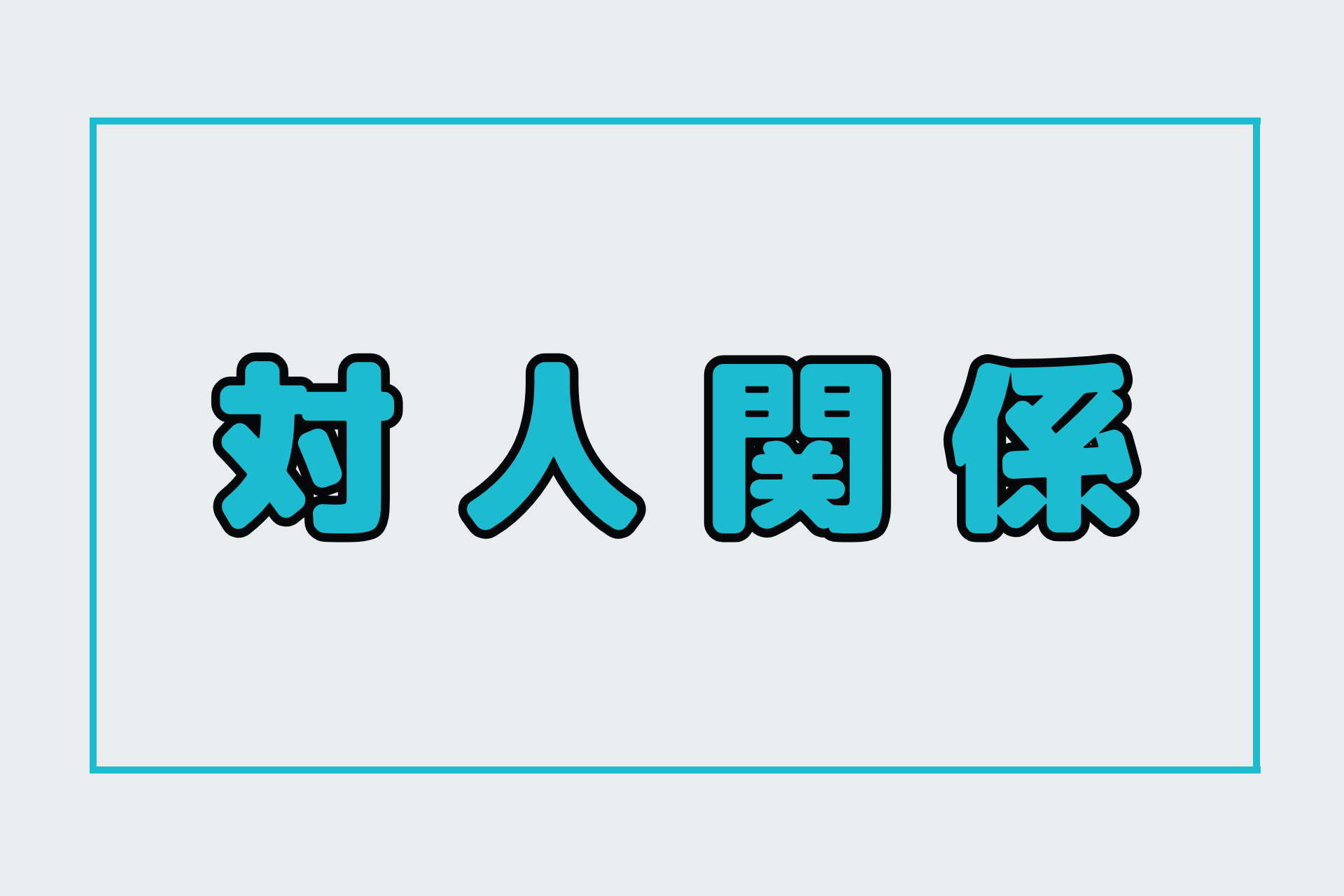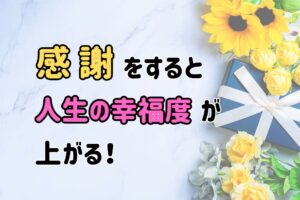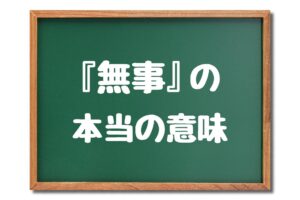あなたは『図に乗る』と聞いてどんなことをイメージしますか?
おそらく、
- 調子づく
- 天狗になる
などのようにネガティブなことをイメージするのではないでしょうか?
しかし、じつは『図に乗る』という言葉は、仏教において非常にポジティブな意味があるのです。
この記事では『図に乗る』という言葉の本来の意味を紹介しています。
図に乗ることの素晴らしさが分かりますので最後まで読んでみてください。
この記事を書いている私『ちょっき』は、お坊さん歴30年。お坊さんに関する裏話や、人間関係の悩みを解消する内容について発信しています。
『図に乗る』ってどういうこと?
先日、家族でショッピングモールへ行き、小学生の息子にゲームソフトを買ってあげました。
夏休み中に【お母さんの言うことをちゃんと聞く】という約束を守ったことへのご褒美だったのです。
ずっと欲しかったゲームソフトを手に入れた息子は大喜び。
そして、「夏休みの宿題を早く済ませて、お手伝いもしたんだからコレも買ってよ。」と言って、さらにもう1つのゲームソフトを指さしました。
そこで私は「今日はコレだけだ、図に乗るんじゃないの!」と一喝。
この『図に乗る』という言葉、私たちは日ごろ《調子づく》という意味で使っています。
しかし、『図に乗る』ことは仏教において非常に素晴らしいことなのです。
一般的な『図に乗る』のイメージ
『図に乗る』という言葉を聞くとネガティブなイメージを抱きますよね。
例えば、
- 調子づいてつけ上がる
- いい気になって自滅する
などです。
なぜ、この言葉にはネガティブなイメージがあるのでしょう?
言葉の意味をひも解いていくと、じつは『図に乗る』という言葉にはまったく異なる側面があるのです。
『図に乗る』はお経から生まれた言葉
『図に乗る』とは、もともと《お経を唱えるとき》に使われる言葉です。
お経というのは、ただ棒読みするのではなく、決められた音程でお唱えするものがあります。
お経の音程のことを【図(ず)】といい、図に合わせて正しく次の音程に変わることを『図に乗る』といいます。
しかし、この『図に乗る』というのは意外と難しいのです。
お経の中には、音程の上げ下げが複雑で、習得が困難なものもあります。
そのため、しっかりと『図に乗る』ことができると、ある種の達成感があります。
つまり、『図に乗る』というのは【難しい課題に取り組んでやり遂げた】ことを意味するのです。
『図に乗る』のは褒められるべきこと
難しい課題をやり遂げると、誰かに褒められますよね。
ですから『図に乗る』のも褒められるべきことなのです。
しかし、難しい課題をやり遂げると、嬉しさのあまり浮かれてしまいがち。
浮かれてしまうと、油断によって普段はしないようなミスをすることもあります。
すると、せっかくの努力が水の泡になったり、他人に不快感を与えてしまうことがあるのです。
そのような【成功の後の慢心】を戒める意味で『図に乗る』と言うようになったことが現在まで続いています。
図に乗ることは素晴らしい
『図に乗る』の本来の意味を知ると、この言葉をもっとポジティブに捉えることができます。
難しいことに挑戦して成功する、努力を積み重ねて大きなことをやり遂げる、それが『図に乗る』ということです。
何かに挑戦し、少しずつ成果が出始めると自信が生まれます。
その自信は、また新たな挑戦の原動力となります。
そうやって自信を深めていくことは、人生を充実させるための大切なプロセスです。
もちろん調子づいてしまうのは要注意です、浮かれてしまっては本末転倒。
しかし、努力の結果として『図に乗る』ことができたのであれば、それは素晴らしいことです。
自分の成長や達成を正しく自覚し、それを糧にして努力を重ねていく姿勢こそが本当の『図に乗る』状態と言えるでしょう。
まとめ
何かに挑戦するのは勇気がいります。
しかし、たとえ小さな一歩でも踏み出すことで、それが未来の大きな成果につながるかもしれません。
最初は少しずつでかまわないので、まずは1年間続けてみてください、そうすれば習慣化します。
そして、それをさらに3年間続ければ、もう初心者レベルは抜け出しているでしょう。
そこからさらに6年間続けると、その分野の先生になっているかもしれません。
あなたも、自分なりの【図】に乗ってみませんか?
失敗しても、またやり直せばいいんです。
挑戦を続け、努力を積み上げることで結果を出すことができ、あなたの人生もきっと豊になるでしょう。
※こちらの記事も読んでみてください。